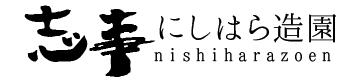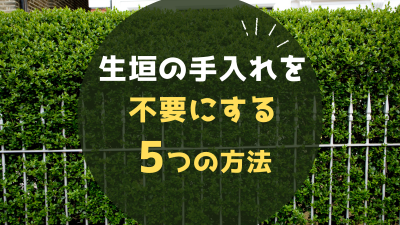生垣の手入れを不要にしたい、と心から感じていませんか?特に、長年ご自宅の庭を彩ってきた生垣が、いつしか悩みの種になってしまうケースは少なくありません。
年齢を重ねるにつれて剪定作業が体力的に辛くなったり、共働きで忙しく、庭の手入れにまで手が回らなかったり…。
「また剪定の時期か…」と気が重くなる、伸びすぎた枝葉の掃除で一苦労、お隣への落ち葉も気になる、そして何より虫の問題。
こうしたストレスから解放されたい、と考えるのは当然のことです。しかし、だからといって無機質なフェンスやブロック塀だけでは、どこか寂しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
「手入れの負担は無くしたい、でも緑のある暮らしも諦めたくない」。そのように感じているなら、ぜひご安心ください。正しい知識と判断基準を持てば、あなたの理想を叶える方法は必ず見つかります。
そこでこの記事では、造園業歴20年の私、西原智が、現場の経験に基づいて「生垣の手入れ」という長年の悩みから解放されるための具体的な方法を、あなたの状況に合わせて解説します。
この記事を読むと以下のことがわかります:
- あなたの状況に合わせて「生垣をやめる」か「続ける」かを判断するための明確な基準
- 今の生垣の手入れに限界を感じている場合の、最善の解決策
- これから目隠しを設置する方が、将来後悔しないための最も重要なポイント
- 生垣をやめる場合の、5つの代替案それぞれの費用と特徴の比較
- 本当に手入れが楽な生垣を選ぶための、プロが実践する3つのポイント
- どこまでがDIYで可能で、どこから業者に頼むべきかの具体的な境界線

西原造園の代表で職人歴20年以上の現役の造園・庭・外構の職人。施工実績500件以上。施主様の生活背景や状況を理解し戸建ての庭のリフォームをメインに外構・造園・エクステリアプランを作成したり、特にお庭の問題を解決するのが得意。全国紙ガーデン&エクステリアの掲載歴があり、父は一級造園技能士、母は奈良新聞にも掲載された一級造園施工管理技士。仕える事と書いた仕事ではなく、志す事と書いた「志事」をするがモットー。
生垣の手入れを不要にしたい!【生垣か代替案か】の判断基準

生垣とは、文字通り「生きている垣根」で、生きている木を並べて植えて垣根(境界)としたものです。敷地と道路、庭と駐車場、庭の中の区切りとして設置されることが一般的です。
そんな生垣ですが、ご自宅の境界やお庭の目隠しについて、「生垣の手入れを不要にしたい」という悩みは、実はスタート地点が異なる2つのケースに分かれます。
一つは、既に存在する生垣の管理に限界を感じている場合。もう一つは、新築の外構などで、これから手のかからない目隠しを設置したいと考えている場合です。
それぞれのご状況によって、最適な解決策は全く異なります。この章では、まずあなたの状況をどちらかに当てはめ、後悔しないための正しい判断基準を解説します。
今の生垣の手入れに限界を感じている場合
長年管理されてきたお庭で、生垣の手入れにもう限界を感じている、というご相談は本当に多くいただきます。
特にご高齢の世帯では、体力的に剪定作業が難しくなり、かといって放置すればご近所の目も気になりますよね。毎年数万円ほどかけて業者に頼むのも、この先10年、20年と考えると大きな負担です。
私の経験上、このような状況で手入れを不要にするための最も確実で、最終的に満足度の高い方法は、思い切って「生垣そのものを無くす」という選択をすることです。
これは決して後ろ向きな決断ではありません。「脚立作業が危険」「毎年の剪定が苦痛」「毛虫が怖い」「落ち葉の掃除で隣人に気を遣う」といった日々のストレスから解放され、安心して暮らすための賢明なリフォームです。
生垣の管理が「趣味」ではなく「苦痛」になってしまったのなら、それは交換を検討すべきサインです。
まずは、生垣を維持し続けることの長期的なコストやリスクと、一度リフォームした場合のメリットを天秤にかけてみましょう。次のステップでは、生垣をやめた場合にどのような選択肢があるのかを具体的に見ていきます。
新しく「手入れ不要の目隠し」を検討している場合
新築の外構を計画中の共働き世帯など、これから手入れ不要の目隠しを設置したいとお考えの場合、将来後悔しないために最も重要なポイントがあります。
それは「植えすぎない」ことです。私の現場でもよくある失敗が、新築時に「緑がたくさん欲しい」と、境界線に沿ってびっしりと木を植えてしまうケースです。
植える本数が増えれば、将来の剪定や掃除の手間は指数関数的に増加します。一度植えた木を撤去するのは、想像以上に大変な作業です。
以前、キンモクセイ1本を抜根するのに、大人8人がかりで2時間もかかった現場がありました。ですから、本当に必要な場所に、必要な本数だけを植える「点の緑化」という考え方が、タイムパフォーマンスを重視する現代の暮らしには合っているのです。
例えば、お隣の窓が気になる場所だけにシンボルツリーを1本植え、残りはフェンスでしっかり目隠しをする。
このようにハード(構造物)とソフト(植物)を組み合わせることで、緑の潤いを楽しみつつ、手入れの手間を最小限に抑えることができます。まずは従来型の「生垣」という発想に固執せず、柔軟な設計を検討することが大切です。
生垣をやめる選択肢|5つの代替案と費用を比較
生垣の手入れが大変で、その負担を感じている方にとって、生け垣の手入れを不要にする最も効果的な解決策は、生垣を伐採して、他の物を取り付けることです。
なぜなら、生垣の手入れには定期的な剪定や肥料の管理、虫対策など、多くの時間と労力が必要となります。
これらの作業は専門的な知識が必要な場合もあったり、何よりも物理的な労力が大変です。
しかし、生垣をやめてしまうと、その代わりに何を設置すれば良いのでしょうか。
つぎに生垣をやめて、生垣以外の代用品についてお伝えします。
はい、承知いたしました。 「生垣をやめる選択肢」としてご紹介した5つの代替案について、それぞれの特徴が分かりやすいように比較表を作成します。
| 代替案 | 初期費用目安 (10m基準) | メンテナンス | 耐久性・安全性 | 特徴・意匠性 |
| 目隠しフェンス | [cite_start]15万〜40万円程度 | ほぼ不要(汚れが気になれば清掃) | 20年以上の耐久性 しっかりとした基礎が必要 | デザインが豊富で、プライバシー確保に優れる |
| ブロック塀 | [cite_start]20万〜30万円程度 | ほぼ不要(汚れが気になれば清掃) | 半永久的だが、地震時の倒壊に注意が必要 | 重厚感と遮音性があるが、圧迫感が強い |
| ラティス (木製) | [cite_start]5万〜15万円程度 | 年1回の塗装が推奨される 木部の腐食に注意 | 5〜10年の耐用年数(木) 強風時に転倒するリスクがある | 通風と採光が良く、植物を絡ませて装飾も可能 |
| ポール (樹脂/アルミ) | 10万〜25万円程度(推計) | 基本的に不要(洗浄程度) | 20年程度の耐久性(樹脂) 風が抜けやすく倒れにくい | モダンで軽やかな印象 隙間の調整で景観と目隠しを両立 |
| フェイクグリーン | 3万〜10万円程度(製品による) | 無し(劣化したら張り替え) | 屋外用はUV加工済み 5〜10年で劣化し交換 | 常に緑を保てる 虫や落ち葉の心配が一切ない |
目隠しフェンス

生垣の手入れを不要にする1つ目の方法はフェンスにする事です。
生垣をフェンスに変えることの最大のメリットは管理が楽になることです。
生垣は定期的な剪定や落ち葉の処理が必要ですが、フェンスにすればこれらの手間が省けます。これにより、空いた時間で、趣味などに時間とエネルギーを使うことができます。
また、フェンスは生垣と比べて耐久性があり、長期間美しい状態を保つことができます。
しかし、一方でデメリットもあります。フェンスは生垣と比べて自然の風合いが少なく、見た目が硬くなる可能性があります
とはいえ、生垣からフェンスに変えると、朝、窓を開けると、手入れの必要ない美しいフェンスが見えます。
これにより、「もう生垣の手入れをしなくて済むんだ」と思うと、毎日の生活が少し楽になり、心に余裕が生まれます。
また、フェンスは生垣と比べて見た目が整っているため、家全体の印象もよくなります。
そんなことから、生け垣の手入れを不要にするものとして、目隠しフェンスが最もお勧めです。
とはいえ、フェンスの設置には初期費用がかかります。どれくらいかかるのか気になりますよね。
そこで次に生垣からフェンスに変える費用についてお伝えします。
フェンスにかかる費用
実は、生垣からフェンスに変更する際の費用は、様々な要素によって変動します。簡単に費用の要素を挙ると次の通りです。
- 撤去費用: まず、既存の生け垣を撤去するための費用が必要です。これには、生け垣の大きさや種類、撤去作業の難易度などが影響します。
- 処分費用: 生け垣の撤去に伴い、発生した廃材の処分費用が必要です。
- フェンスの種類と材質:アルミやスチール、木製など、フェンスの材質によって価格は大きく異なります。また、デザインや機能性も費用に影響します。
- フェンスの長さ:フェンスが長ければ長いほど、本体や部品の数が必要になり、値段が上がります。
- フェンスの高さ:フェンスの高さによっても費用は大きく変わってきます。高ければ高いほど、フェンスの値段は上がります。
- 工事費: ブロック塀の設置には専門的な技術が必要なため、専門業者に依頼することが一般的です。そのため、工事費が発生します。
具体的な費用については、お住まいの地域や選択するフェンスの種類、業者によりますので、具体的な数値を出すことは難しいです。
また、生垣からフェンスに変える場合は、フェンスの設置費用以外に、生け垣の撤去費用がかかります。
そのため、フェンスを取り付ける場合は、生け垣の撤去費用も掛かるという事を念頭に置いておくと良いでしょう。
それらも踏まえると、およその金額ををお伝えすると、50万円~100万円以上はみておいた方が良いでしょう。
具体的な費用を知りたい場合は、地元の業者に直接問い合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
ブロック塀

生垣の手入れを不要にする方法として、ブロック塀に造り変えるという方法もあります。
ブロック塀は、単に既製品のブロックを積み上げるだけではなく、天然石を張ってオシャレにしたり、塗り材で壁を塗ることでおしゃれにしたり、最近では壁にボードを張っておしゃれに見せたり、様々なバリエーションがあります。
そのバリエーションの多さがブロック塀の魅力の1つでもあります。
それ以外にも、ブロック塀の基本的なメリットがあります。
基本的なメリットとしては、やはりその耐久性が挙げられます。外構の専門業者が鉄筋を入れて施工したブロック塀は、約30年の耐用年数を誇ります。
また、汚れが目立ってきたときには高圧洗浄機で洗い流すだけでお手入れが可能で、災害や事故がなければ、定期的なメンテナンスだけで長期間使い続けられます。
さらに、ブロック塀にする事で、フェンスと比べて隙間が少ないため、簡単に登ることができないので、敷地内への侵入を防げます。
また、隙間がないのでフェンスよりも目隠しの効果が高まります。
一方、ブロック塀のデメリットとしては、近年の施工不良のブロック塀が倒れてしまい、悲惨な目に合ったニュースなどの影響による、耐震性への不安が挙げられます。
また、風を通さないため、家の通風性が悪くなる可能性があります。さらに、壁が高いと隠れる場所が増えるので、空き巣などの被害が起こり得る可能性もあります。
ブロック塀の費用について
生垣からブロック塀に変える場合の費用についても、様々な要素によって変動します。簡単に費用の要素を挙ると次の通りです。
- 撤去費用: まず、既存の生け垣を撤去するための費用が必要です。これには、生け垣の大きさや種類、撤去作業の難易度などが影響します。
- 材料費: ブロック塀を設置するための材料費が必要です。ブロックの種類や大きさ、デザインにより費用は変動します。
- 工事費: ブロック塀の設置には専門的な技術が必要なため、専門業者に依頼することが一般的です。そのため、工事費が発生します。
- 処分費用: 生け垣の撤去に伴い、発生した廃材の処分費用が必要です。
- その他の費用:ブロック塀周りの地面の処理等。
費用については、ブロック塀の面積や施工方法により大きく異なります。
化粧ブロックを採用すると、見た目はおしゃれになりますが、費用は高くなる傾向があります。また、フェンスと比べてブロック塀の方が相場価格は高いとされています。
それらも踏まえると、およその金額ををお伝えすると、60万円~100万円以上はみておいた方が良いでしょう。
具体的な費用を知りたい場合は、地元の業者に直接問い合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
ラティスで目隠し

生垣の手入れを不要にする方法として、ラティスで目隠しをするという方法もあります。
ラティスは、簡単に取り付けられる同時に、お庭を彩るおしゃれなアクセントポイントの1つになるだけでなく、適切なプライバシーを提供します。
また、ラティスは、様々な素材、デザイン、サイズで利用できます。
木製のラティスは、自然な雰囲気を好む方におすすめです。
また、プラスチック製のラティスは、耐久性とメンテナンスの容易さを求める方に適しています。
さらに、ラティスは植物を這わせたり、プランターをひっかけておくための支えとしても使用でき、緑豊かな目隠しを作ることができます。
例えば、お庭に自然な雰囲気を求めておられるなら、木製のラティスにつる性の植物を絡ませることで、美しい緑の壁を作ることができます。
それにより、視覚的な魅力を加えながら、必要なプライバシーを提供します。
しかし、ラティスには大きなデメリットがあります。
それは何かというと、経年劣化が激しいという事です。
特に木製のラティスは、紫外線や風雨にさらされ、放っておくと腐って朽ちていき、お庭の見栄えが大きく損なわれます。また、朽ちてきて、ラティスの格子が外れたりもします。
プラスチック製や樹脂製のラティスの場合だと、朽ちる事がないので、長持ちします。

とはいえ、色あせたり、苔やカビなどにより見た目が悪くなる事があるのでご注意ください。
また、植物を絡ませる場合は、当然植物も育ち生え茂るので、適切な手入れが必要となります。
ラティスは生垣の代わりになる素晴らしい選択肢ですが、経年劣化が激しいということを忘れないでください。
ラティスの費用について
生垣からラティスに変える場合の費用については次のような要素があります。
- 撤去費用: まず、既存の生け垣を撤去するための費用が必要です。これには、生け垣の大きさや種類、撤去作業の難易度などが影響します。
- 処分費用: 生け垣の撤去に伴い、発生した廃材の処分費用が必要です。
- 工事費: メッシュフェンスの設置には専門的な技術が必要なため、専門業者に依頼することが一般的です。そのため、工事費が発生します。
- ラティスの種類と材質:プラスチック製や樹脂製、木製など、ラティスの材質によって価格は大きく異なります。また、デザインや機能性も費用に影響します。
- 高さと、長さ:フェンスと同様に高さと長さも費用に影響します。
費用について、ラティスはホームセンターでも手軽に入手できる事と、DIYで取り付ける事もできるので、費用は比較的抑える事ができます。
とはいえ、DIYで簡単にラティスを取り付けたい場合は、フェンスに結束バンドで結びつけるという方法で施工される方が多いです。
そのため、生け垣を撤去してラティスを取り付ける場合は、メッシュフェンスを先に立てて、メッシュフェンスにラティスを取り付ける事を想定しておくと良いでしょう。
メッシュフェンスはフェンスの中でも最も安いフェンスなので、比較的値段も抑えられます。
それらも踏まえると、およその金額ををお伝えすると、30万円~60万円以上はみておいた方が良いでしょう。
具体的な費用を知りたい場合は、地元の業者に直接問い合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
ポールで目隠し

生垣の手入れを不要にする方法として、ポールで目隠しをするという方法もあります。
ポールを使った目隠しは、視線を気にする方にとっては非常に有効な選択肢です。
特に、壁やフェンスを設置すると圧迫感を感じてしまう方には、ポールが最適です。
なぜかというと、ポールは適度な間隔をあけることで、デザイン的にも素敵に見えるからです。
また、オープンガーデンにとても合う外構エクステリア商材とも言えます。
例えば、木の質感のあるポールを使って、横一直線に並べたり、互い違いにしてならべたり、緩やかにカーブするように並べたり、並べ方がにバリエーションができるので、フェンスやブロック塀とはまた違ったオシャレを演出することができます。
デメリットとしては、フェンスやブロック塀よりも隙間が出来る事がデメリットの1つで、目隠しをメインで考えたい人や、防犯が気になる方にとっては、不向きな商品でもあります。
ちなみに、枕木を立てて使う事はあまりお勧めできません。なぜなら、枕木は数年後に必ず腐るからです。
なので、ポールを建てる場合は、コンクリート製やアルミ製のものを使用することをお勧めします。
ポールの費用について
生垣からポールに変える場合の費用については次のような要素があります。
- 撤去費用: まず、既存の生け垣を撤去するための費用が必要です。これには、生け垣の大きさや種類、撤去作業の難易度などが影響します。
- 処分費用: 生け垣の撤去に伴い、発生した廃材の処分費用が必要です。
- 工事費: ポールの設置には専門的な技術が必要なため、専門業者に依頼することが一般的です。そのため、工事費が発生します。
- ポールの種類と材質:コンクリート製やアルミ製など、ポールの材質によって価格は大きく異なります。また、デザインや機能性も費用に影響します。
- 高さと、長さ(距離=本数):フェンスと同様に高さと長さも費用に影響します。距離が長いとポールの本数も増えていきます。
ポールはホームセンターで見つける事は難しいので、ネット通販で買う方が入手しやすいでしょう。
とはいえ、ネット通販でも見つけにくい商品なので、DIYで作るのは商品が入手しにくいというのが難点です。
なので、地元のエクステリア・外構・造園業者さんに相談して頂く方が早いでしょう。
それらも踏まえると、およその金額ををお伝えすると、30万円~60万円以上はみておいた方が良いでしょう。
具体的な費用を知りたい場合は、地元の業者に直接問い合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
フェイクグリーンをフェンスに巻きつける
フェンスやブロック塀だと無機質ですよね。とはいえ、生け垣だと管理が大変。そんな時に、違う選択肢としてフェイクグリーンを使うとという方法もあります。
フェイクグリーンとは、植物を模した人工の植物のことで、枯れることなく、水やりや肥料などの手間が不要で、どんな環境にも設置可能です。
とはいえ、メリットデメリットもあります。
メリット:
- 枯れる心配がない:フェイクグリーンは生物ではないため、枯れることはありません。特に植物の世話が苦手な人にとって大きな利点となります。
- 手間がかからない:水やりや肥料、害虫対策など、生物の植物に必要な手間が一切不要です。
- 環境を選ばない:日当たりや温度、湿度など、生物の植物が必要とする特定の環境を必要としません。どのような場所にも設置可能です。
デメリット:
- 植物の世話を楽しむことができない:植物の成長を見守る楽しみや、育てる過程を楽しむことはできません。
- 埃や汚れが付きやすい:フェイクグリーンは埃や汚れが付きやすいため、定期的な掃除が必要となる場合があります。
- 安っぽい印象を与える可能性:フェイクグリーンは見た目が安っぽく見えることがあります。しかし、最近のフェイクグリーンは非常に精巧に作られており、一見すると本物と区別がつかないものもあります。
- 耐久性が短い:一般的にフェイクグリーンの耐用年数は5年から10年と言われていますが、屋外での使用は、雨ざらしになったり、紫外線の影響などで痛むのが速いです。
フェイクグリーンは使用環境にもよりますが、付け替えが必要となる事を想定して使用すると良いでしょう。
フェイクグリーンの費用について
生垣からフェイクグリーンに変える場合の費用については次のような要素があります。
- 撤去費用: まず、既存の生け垣を撤去するための費用が必要です。これには、生け垣の大きさや種類、撤去作業の難易度などが影響します。
- 処分費用: 生け垣の撤去に伴い、発生した廃材の処分費用が必要です。
- 工事費: フェンスの設置には専門的な技術が必要なため、専門業者に依頼することが一般的です。そのため、工事費が発生します。
- フェイクグリーンの種類や材質:フェイクグリーンはリアルなものほど高くなる傾向にあります。とはいえ、見た目がリアルな物の方がより自然なのでお勧めです。
- 高さと、長さ(距離=本数):フェイクグリーンと同様に高さと長さも費用に影響します。距離が長いとポールの本数も増えていきます。
費用的には、メッシュフェンスと言ったフェンスの中でも最も安いタイプのフェンスに巻き付ける事ができるので、比較的安価で、生け垣をやりかえる事ができます。
また、フェンスの設置は専門業者に、フェイクグリーンはDIYで取り付けるという事も可能なので、費用を押させることができます。
およその金額ををお伝えすると、業者に依頼した場合、30万円~60万円程度はみておいた方が良いでしょう。
具体的な費用を知りたい場合は、地元の業者に直接問い合わせて見積もりを取ることをおすすめします。
※フェンスだけ業者さんに作ってもらって、フェイクグリーンはご自身で購入して、DIYで簡単に取り付けられます。
手間のかからない生垣を選ぶ|プロが厳選するおすすめ樹種25選
手間のかからない生垣を選ぶ3つのポイント
「手間のかからない生垣」を設置すると決めた方が、次に直面するのが「では、どの木を選べばいいのか?」という問題です。
ホームセンターや園芸店には多くの種類の庭木が並んでいますが、見た目の好みだけで選んでしまうと、後々大変な手間がかかることも少なくありません。
ここでは、まず最初に私たちプロが樹種選定の際に必ずチェックする、後悔しないための重要なポイントを解説します。この基準を知るだけで、あなたの生垣づくりは成功に大きく近づきます。
ポイント1:刈り込みが出来る植木を植える
生垣のお手入れを楽にするためには、刈り込みが可能な植木を選んで植えることが大切です。
例えば、ツゲやヒイラギなどの常緑樹は、形を整えやすく、刈り込みに適しています。
これらの植木は、成長が比較的遅く、刈り込みを頻繁に行う必要がないため、お手入れが楽になります。
結論として、生垣のお手入れを楽にするためには、刈り込みが可能で、成長が遅い植木を選ぶことがおすすめです。
ポイント2:成長の遅い植木を植える
生垣のお手入れを楽にするためには、成長の遅い植木を選んで植えることがおすすめです。
理由は、成長が遅い植木は、頻繁に剪定する必要がなく、その結果、お手入れが楽になるからです。
例えば、エゴノキやソヨゴなどの常緑樹は、成長が比較的遅く、剪定を頻繁に行う必要がないため、お手入れが楽になります。
ポイント3:病害虫に強い植木を選ぶ
せっかく植えた生垣が、ある日突然、毛虫だらけになってしまった…という経験はありませんか?実は、手入れの手間を考えた時、剪定の頻度以上に重要かもしれないのが、「病害虫に強い」という性質です。
特に、ツバキやサザンカに発生しやすいチャドクガのような毒毛虫は、ご家族の健康にも関わるため、一般のご家庭では絶対に避けたいトラブルですよね。
私たちの現場では、「手入れが楽な木を」とご希望の方には、こうした定期的な消毒が必要になる可能性が高い樹種よりも、「病害虫に強い植木」をお勧めしています。
例えば、クチナシはオオスカシばという大きな幼虫がつきやすく、ツゲも近年ツゲノメイガの被害が深刻です。どんなに成長が遅くても、こうした害虫管理という「不快な手間」が発生してしまっては本末転倒です。
ですから、樹木を選ぶ際は、まずその品種が病害虫に強いかどうかを確認することが、手入れを不要にしたいという目的を達成するための第一歩になります。
次の章では、具体的な作業について、DIYと業者依頼の境界線を考えていきましょう。
手間のかからない生垣と言えども、植木は生き物なので、放っておくとどんどん伸びていきます。
そのため、剪定は必ず必須になってきます。また落ち葉も落ちるので、定期的な落ち葉掃除も必須になってきます。
剪定や落ち葉掃除を全くしたくない場合は、フェンスやブロック塀を検討しましょう。そのため、剪定は必ず必須になってきます。また落ち葉も落ちるので、定期的な落ち葉掃除も必須になってきます。
【洋風でおしゃれ】おすすめの生垣 8選
あなたが、フェンスやブロック塀も良いけど、やっぱり生垣が良いという場合、「じゃあ庭の生垣の木には結局何を植えたらいいの?」と思われますよね。
そこで、次に手入れがかからない生垣として人気の常緑中低木の種類を詳しくご紹介します。
剪定の手間が少なく、おしゃれで洋風の雰囲気を出せる植物たちをご紹介します。
| 樹種名 | タイプ | 成長速度 | 推奨剪定回数 | 特徴 | 注意点 |
| マサキ | 常緑・中木 | やや早い | 年に数回 | ・日本全国に分布し、丈夫で育てやすい ・剪定に強く、垣根として使いやすい | ・うどん粉病や害虫の被害に遭うことがある ・真夏の剪定は避けるのが理想 |
| プリペット | 常緑・中木 | 早い | 年2~3回 | ・葉が密生し、目隠しに向く ・成長が旺盛で、早く生垣を作りたい場合に適する | ・寒さに弱く、地域によっては冬に落葉する ・ハマキムシの被害を受けやすい |
| レッドロビン | 常緑・中木 | 早い | (随時可能) | ・新芽が鮮やかな赤色で美しい ・刈り込みに強く、季節を問わず剪定可能 | ・寒冷地では生育が悪い場合がある ・特定の病害虫の被害に遭うことがある |
| トキワマンサク | 常緑・中木 | 早い | (随時可能) | ・春に咲くヒモ状のユニークな花が特徴 ・近年、垣根としての利用が増えている | ・寒さに弱く、寒冷地での生育は難しい ・枝が四方八方に広がりやすい |
| フェイジョア | 常緑・中木 | 緩やか | (随時可能) | ・美しい花と、食用になる果実が楽しめる ・耐寒性があり、-10℃程度まで耐える | ・刈り込みではなく、枝を間引く「透かし剪定」が必要 ・日陰では花や実がつきにくい |
| ヒメシャリンバイ | 常緑・低木 | 遅い | 年1回(春) | ・葉が小さく光沢があり、上品な印象 ・寒さに強く、日本全国で育てられる | ・カイガラムシの対策が必要 |
| ボックスウッド | 常緑・低木 | 普通 | (随時可能) | ・明るい葉色で洋風の庭に合う ・刈り込みに非常に強く、好きな形にしやすい | ・寒さにやや弱く、冬に葉が褐色になることがある ・風通しが悪いと害虫被害に遭いやすい |
| アベリア | 常緑・低木 | 中程度 | 年1~2回 | ・春から秋まで長期間、白やピンクの可愛い花が咲く ・寒さに強く、育てやすい | ・厳しい冬には霜焼け対策が必要 ・湿度が高いと病気になりやすい |
マサキ(常緑・中木)

項目 | 詳細 |
特徴 | マサキはニシキギ科の常緑樹で、北海道南部から九州まで日本全国に分布します。丈夫で成長が早く、剪定にも強いため、庭木や垣根としてよく使われます。 |
開花の有無と時期 | 開花は6~7月で、新枝にある葉の付け根から伸びた花序に直径5ミリほどの花が多数集まって咲きます。 |
果実の有無と時期 | 果実は10月~1月になると淡い紅紫色に熟して、3~4つに裂けて種子が飛び出します。 |
耐候性の有無と理由 | 耐寒性があり、北海道南部以南であれば植栽できます。しかし、本来は暖地を好みます。大気汚染や強度の乾燥過湿にも耐えます。 |
成長速度 | 成長はやや早いです。 |
適した成育環境 | 日向を好むが、耐陰性が高く半日陰でも育ちます。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。年に数回剪定が必要です。いつ行ってもOKですが、初夏か秋口が理想。真夏は控える。 |
耐病性と理由 | 病害虫にやや弱く、ウドン粉病に罹患することやカイガラムシ、ハマキムシの被害にあうことがあります。 |
プリペット(常緑・中木)

項目 | 詳細 |
特徴 | 中国及びヨーロッパを原産とする常緑低木。葉が密生し、公園や商業地の植え込みなどに多用される。成長が旺盛で、ネズミモチやイボタノキの仲間。 |
開花の有無と時期 | 刈り込みをせずに放任すれば初夏に白い花を咲かせる。ただし、花の観賞を目的にするような木ではない。 |
果実の有無と時期 | 花が咲くので実もできるが、観賞用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さに弱く、地域によっては冬期に落葉する。また、暖地に植えた場合でも環境に慣れるまでは冬期に落葉することがある。 |
成長速度 | 成長が早い。 |
適した成育環境 | 半日陰でも育つが、基本的には日向を好む樹種。日陰に植えると枝葉が間延びすることがある。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。最低でも年2~3回の手入れが必要。前年の秋以降に剪定をしなければ開花しやすい。 |
耐病性と理由 | ハマキムシの被害を受けやすい。被害を受けた茶色い葉は早期に取り除く。 |
レッドロビン(常緑・中木)

項目 | 内容 |
特徴 | 新芽の赤味が際立つ。刈り込んだ後は時季を問わず赤い芽が出る。春には真っ白な小花を咲かせ、秋には赤い実をつける。 |
開花の有無と時期 | 開花は5・6月ころ。ただし頻繁に刈り込まれることが多いため花を楽しむ木という印象は乏しい。 |
果実の有無と時期 | 秋に赤い実をつける。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さにやや弱く、寒冷地では生育の悪い場合がある。 |
成長速度 | 成長が早い。 |
適した成育環境 | 日向を好む。有機質の多い肥沃な土壌を好む。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。季節を問わず剪定可能。ただし、夏場に強い剪定を行うと病害の発生を誘発する可能性がある。 |
耐病性と理由 | かつては病気になりにくいとされたが、根頭がん腫病やゴマ色斑点病、カイガラムシの被害などに遭うことがある。 |
トキワマンサク(常緑・中木)

項目 | 内容 |
特徴 | 5月頃にマンサクに似たヒモ状の花を咲かせる。一年中葉をつけているため常盤満作と名付けられた。近年垣根に利用されることが増えてきた。 |
開花の有無と時期 | 5月頃に開花する。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
耐候性の有無と理由 | 寒さに弱いため、東北や北海道などの寒冷地では生育が難しい。 |
成長速度 | 成長が早い。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。放任すると徒長枝が増えたり株が大きくなり過ぎる。また枝が四方八方に広がりやすい。 |
耐病性と理由 | 病気には比較的強いが、苗木を植え付けるにコウモリガの被害に合う頃がある。コナジラミ、ミノムシ、ハマキムシが出てくる事もある。 |
フェイジョア (常緑・中木)

項目 | 内容 |
特徴 | ウルグアイやパラグアイなど中南米を原産とする亜熱帯の果樹。食用となる実もさることながら花も美しいため日本でも庭木として使われる。 |
開花の有無と時期 | 開花は5~6月。蕊しべが目立つ花の作りは同じ時期に咲くビヨウヤナギやキンシバイに通じるものがある。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 11月ごろに熟す果実は甘くパイナップルのような香りがある。実が落ちる前に収穫し、しばらく寝かせたものを生で食べたりジャムにして食べたりもできる。 |
耐候性の有無と理由 | 原産地を見れば分かるように温暖な地を好むが成木であれば冬場に気温がマイナス10度になるような場所でも耐える。ただし寒風には弱いため風当たりの強い場所は避けるか囲いを設けるとよい。 |
成長速度 | 緩やか |
適した成育環境 | 日差しを好む陽樹であり日陰では花や実ができにくい。 |
年間の剪定回数と時期 | 剪定には耐えるが、刈り込みばさみで刈り込むような木ではない。密生した枝を根元から間引くような剪定が適する。透かし剪定が必要なため、素人では剪定がやや難しい。 |
ヒメシャリンバイ(常緑・低木)

項目 | 内容 |
特徴 | バラ科・シャリンバイ属の一種で低木で植栽されることが多い。ヒメシャリンバイは、シャリンバイに比べ葉は小さく、光沢があります。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は5月から6月です。 |
常緑か落葉か | 常緑です。 |
果実の有無と時期 | 果実があります。果実の熟す時期は秋です。食用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があります。寒さに強く、日本全国で育てることができます。 |
成長速度 | 成長速度は遅いです。 |
適した成育環境 | 日向でも日陰でも生育が可能。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。年に1回、春に剪定を行います。ただし、成長が遅いため、必要に応じて剪定を行います。 |
耐病性と理由 | カイガラムシが天敵。カイガラムシ対策を行っておく。 |
ボックスウッド(常緑・低木)

項目 | 内容 |
特徴 | 明るい葉色が特徴で、洋風のガーデンに相性が良い。刈り込みに耐えるため、公共スペース等の植え込みにも利用される。丈夫で初心者にも育てやすい。 |
開花の有無と時期 | 3~4月頃に花を咲かせるが観賞用ではない。 |
常緑か落葉か | 常緑性の低木。だし、寒さにやや弱く冬期には葉が褐色に変化する。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があり、刈り込みにもよく耐える。とはいえ、寒さにやや弱く、冬期には葉が褐色に変化する。 |
成長速度 | 早くもなく、遅くもない。 |
適した成育環境 | 基本的には日向が好きな木だが、日陰にも耐える。土質もよほどの荒地でなければ問題はない。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。春先から夏前もしくは秋ごろに剪定。刈り込みに強いため、好きな形に剪定できる。 |
耐病性と理由 | 風通しの悪い場所ではハマキムシや蛾の幼虫の被害に遭いやすい。 |
アベリア(常緑・低木)

項目 | 内容 |
特徴 | アベリアは、常緑の低木で、花が美しいことで知られています。葉は小さく、光沢があり、密に茂っています。花は小さく、白色またはピンク色で、長い期間にわたって咲きます。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花期は春から初夏にかけてで、一部の品種では秋にも再び花を咲かせます。 |
常緑か落葉か | 常緑の低木です。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さに強いです。しかし、厳しい冬季には霜焼けを避けるために保護が必要です。 |
成長速度 | 成長速度は中程度です。 |
適した成育環境 | 日当たりの良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。花を多く咲かせたい場合は日なたに植え付ける方が良い。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。年に1~2回、花が終わった後の初夏に剪定します。 |
耐病性と理由 | 一般的に病害虫に強いですが、特に湿度が高い環境では病気になりやすいです。 |
【和風で落ち着いた】おすすめの生垣 6選
| 樹種名 | タイプ | 成長速度 | 推奨剪定回数 | 特徴 | 注意点 |
| サツキ | 常緑・低木 | 早い | 年1回(花後) | ・日本原産のツツジの一種で育てやすい ・初夏に美しい花を咲かせる | ・寒風に弱く、寒冷地では半落葉になることがある ・花後にすぐ剪定しないと翌年の花が減る |
| イヌツゲ | 常緑・低木 | 遅い | 年1~2回 | ・枝葉が密に茂り、目隠しに向く ・寒さに強く、寒冷地でも育てられる | ・湿度が高いと根腐れ病などになりやすい ・雌株にだけ黒い実がつく |
| イヌマキ | 常緑・高木 | やや遅い | 年1~2回 | ・土質を選ばず丈夫で、病害虫が少ない ・大気汚染や潮風にも強い | ・暖かい気候を好む |
| ツバキ(椿) | 常緑・広葉樹 | やや遅い | 年1回(花後) | ・冬から春にかけて大きく美しい花を咲かせる ・日陰でも育つ | ・強い寒さや乾燥、霜に弱い ・湿度が高いと黒星病に感染しやすい |
| サザンカ(山茶花) | 常緑・低木 | 遅い | 年1回(花後) | ・秋から冬にかけて花を咲かせる ・寒さに強く、日本の冬でも生育可能 | ・強い寒波には弱いため、寒冷地では保護が必要 ・湿度が高いと病気になりやすい |
| ヒイラギ(柊) | 常緑・低木 | 遅い | 年1回(早春) | ・葉のトゲが防犯対策になる ・寒さに強く、日本全国で育てられる | ・水はけが悪いと根腐れ病に注意が必要 ・冬に赤い実がなり観賞できる |
サツキ(常緑・低木)

項目 | 内容 |
特徴 | ツツジの一種で、日本原産。江戸時代に多くのツツジの品種が作り出され、4月~5月に咲くものをツツジ、5月~6月に咲くものをサツキと区別するようになった。 |
開花の有無と時期 | 開花あり。開花時期は5月下旬から6月上旬。 |
常緑か落葉か | 常緑。 |
果実の有無と時期 | 果実あり。花の後にできる実はさく果(熟すると下部が裂け、種子が散布される果実)。食用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性あり。丈夫な性質を持つため、庭木や盆栽として広く栽培される。ただし、寒さにも強い。しかし寒風には弱いため、東北や北海道などの寒冷地では、冬に葉を落とす半落葉性になることもある。 |
成長速度 | 成長速度は早い。 |
適した成育環境 | 日陰でも育つが、基本的に日光を好むので、日なたでの植栽がよい。花を咲かせたい場合は日なたの方がよい。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。5月~6月頃、花が終わり次第剪定する。6月~7月頃に花芽が付く。初夏以降の剪定は花芽も刈る事になるので、翌年の花付きが悪いと感じられる事がある。 |
耐病性と理由 | 耐病性は、丈夫で病害虫にも強い。まれにカミキリやハマキムシの被害に遭うことがある。 |
イヌツゲ

項目 | 内容 |
特徴 | イヌツゲは、高さが1.5〜2mに成長する低木で、枝が広がり、密に茂る。葉は対生し、形状は楕円形から卵形、色は濃緑色で光沢がある。葉の長さは約5〜10cmで、葉の縁には鋸歯がある。 |
開花の有無と時期 | 春(4〜5月)に白い花を咲かせる。観賞用としては向かない。 |
常緑か落葉か | 常緑の低木。 |
果実の有無と時期 | 雌雄異株のため、雌株にだけ黒い果実がつく。食用でもなく、観賞用でもない。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さに強い植物で、耐寒性がある。そのため、寒冷地でも育てることが可能である。 |
成長速度 | 成長速度は比較的遅い。 |
適した成育環境 | 日当たりの良い場所を好むが、半日陰でも育つ。湿度が高い場所を好み、排水の良い土壌を好む。。 |
年間の剪定回数と時期 | 年に1〜2回、春と秋に剪定を行う。剪定は枝の成長を抑え、形状を整えるために行われる。 |
耐病性と理由 | 比較的病害虫に強いが、湿度が高いと病気になりやすい。特に、根腐れ病や葉斑病に注意が必要である。 |
イヌマキ

項目 | 内容 |
特徴 | 土質を選ばず丈夫に育ち、病害虫の被害も比較的少ない。大気汚染や潮風にも強く、都市部や沿岸部の防風林や垣根として盛んに使われる。 |
開花の有無と時期 | 5~6月ごろに雌雄それぞれの花が葉の脇に咲く。観賞用ではない。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 雌の木にできる実は団子状で、10~12月に赤黒く熟す。観賞用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があり、耐寒性は強い。しかし、基本的には暖かい気候を好む。 |
成長速度 | やや遅い |
適した成育環境 | 日向を好むが、日陰にも耐える。刈り込みに強い。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。年2回が理想だが、年1回の剪定でも問題はない。5月頃か、秋口に剪定を行う事が理想。 |
耐病性と理由 | 病害虫の被害が比較的少ない。 |
ツバキ(椿)

項目 | 内容 |
特徴 | ツバキは、常緑の広葉樹で、花は大きく美しい。花色は主に白や赤で、一部の品種ではピンクや黄色の花を咲かせる。花びらは一重や八重など、品種により異なる。 |
開花の有無と時期 | 開花する樹木で、開花時期は品種により異なるが、一般的には冬から春にかけて(11月から4月頃)が主な開花時期である。 |
常緑か落葉か | 常緑樹 |
果実の有無と時期 | 果実はつく。観賞用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | ツバキは寒さに強い耐候性を持つ。しかし、強い寒さや乾燥には弱く、特に花は霜に弱い。 |
成長速度 | やや遅い。 |
適した成育環境 | 日陰でも育つが、より良い花を咲かせるためには日なたもしくは、半日陰が適している。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。ツバキの剪定は年に1回、主に花が終わった後の春に行われる。 |
耐病性と理由 | 一般的には病害に強いが、湿度が高いと黒星病に感染しやすい。 |
サザンカ(山茶花)

項目 | 内容 |
特徴 | サザンカは、ツバキ科ツバキ属の常緑低木で、日本をはじめとする東アジア原産です。花は秋から冬にかけて咲き、花色は白から深紅まで様々です。葉は厚くて光沢があり、濃い緑色をしています。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は秋から冬(10月から2月)です。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 果実をつけます。果実は緑色で、秋に成熟します。観賞用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があります。寒さに強く、日本の冬でも生育できます。ただし、強い寒波には弱いため、寒冷地では保護が必要です。 |
成長速度 | 成長速度は遅いです。 |
適した成育環境 | 日当たりの良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。 |
年間の剪定回数と時期 | 年に1回、花が終わった後の春(3月から4月)に剪定します。 |
耐病性と理由 | 病害虫には比較的強いですが、黒星病や葉斑病に感染することがあります。これらの病気は湿度が高いと発生しやすいため、通気性を良くすることが重要です。 |
ヒイラギ(柊)

項目 | 内容 |
特徴 | ヒイラギは、常緑の低木で、葉は対生し、形は楕円形から卵形、先端はとがり、縁には鋭い鋸歯があります。葉の表面は光沢があり、濃い緑色をしています。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は11月~12月に、小さな白い花を咲かせます。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 果実はつきます。果実は初冬に赤い実をつける。観賞用としても好まれている。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があります。寒さに強く、日本全国で育てることができます。 |
成長速度 | 成長速度は遅いとされています。 |
適した成育環境 | 日当たりの良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。剪定は年に1回、新芽が出る前の早春(2月から3月)に行います。 |
耐病性と理由 | ヒイラギは比較的病害虫に強いとされていますが、根腐れ病に注意が必要です。水はけの悪い土壌や過湿により発生します。 |
【花が咲く生垣】でおすすめの樹木7選
| 樹種名 | タイプ | 成長速度 | 推奨剪定回数 | 特徴 | 注意点 |
| キンモクセイ | 常緑・広葉樹 | やや早め | 年1回(秋) | ・秋にオレンジ色の小花が咲き、甘い香りが広がる ・病害虫に強い | ・寒さ、乾燥、潮風にやや弱い ・日向でないと花付きが悪くなる |
| ドウダンツツジ | 落葉性 | 緩やか | (随時可能) | ・春の可憐な花と、秋の美しい紅葉が楽しめる ・丈夫で害虫がつきにくい | ・剪定を怠ると下枝がなくなりやすい ・真夏の剪定は避ける |
| ブラシノキ | 常緑・低木 | やや遅い | 年1回(花後) | ・名前の通り、赤いブラシ状のユニークな花が咲く ・寒さに強く、日陰でも育つ | ・花を多く咲かせたい場合は日向で水はけを良くする ・刈り込みより枝を間引く剪定がおすすめ |
| カラタネオガタマ | 常緑樹 | 遅い | 年1回(花後) | ・バナナに似た甘い香りの花が咲く ・樹形が自然に整いやすい | ・寒さにやや弱く、冬の寒風を嫌う ・風通しが悪いと害虫が発生することがある |
| チャイニーズホーリー | 常緑・低木 | やや遅い | 年1回(春) | ・春の小花と、冬になる赤い実が楽しめる ・病気に強く、寒さにも強い | ・強い日差しが苦手で、半日陰が適している |
| ユキヤナギ | 落葉・低木 | 速い | 年1回(花後) | ・春に、枝垂れた枝を覆うように白い小花が咲く ・耐寒性が強く、育てやすい | ・成長が早いため、剪定は必須 ・うどんこ病やカイガルメシに注意が必要 |
| ローズマリー | 常緑・ハーブ | 中程度 | (随時可能) | ・長期間にわたり、紫や青の可憐な花が咲く ・乾燥に強く、香りも楽しめる | ・非常に寒冷な気候には弱い ・多湿な環境ではうどん粉病になることがある |
キンモクセイ

項目 | 内容 |
特徴 | モクセイ科の常緑広葉樹。樹皮はサイの皮に似る。葉は濃緑色で革質。 |
開花の有無と時期 | 開花あり。開花時期は9~10月。その年にできた葉の付け根にオレンジ色の小花を密生させる。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 果実は見当たらない。日本には雄株しかないため、果実を見ることはほぼできない。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さにやや弱い。乾燥、潮風、煙害に弱い。 |
成長速度 | 成長はやや早め。放置するとどんどん広がっていくので注意が必要。 |
適した成育環境 | 日陰でも育つが、花をより多く咲かせるには日向に植える必要がある。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。年1回の剪定でも問題はない。花が終わってから、秋ごろの剪定がよい。 |
耐病性と理由 | 病害虫に強い。ただし、空気が汚れていると花付きは悪くなる。 |
ドウダンツツジ

項目 | 内容 |
特徴 | 丈夫で害虫がつきにくい。花が咲いて紅葉も美しい。葉は菱形で新枝は赤みを帯びる。 |
開花の有無と時期 | 開花する。開花時期は4~5月。観賞用としても人気。 |
常緑か落葉か | 落葉性 |
果実の有無と時期 | 果実ができるが、観賞用ではない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐寒性、耐暑性があり、乾燥や病害虫にも強い。 |
成長速度 | 成長が緩やかで大きくなるまでに時間がかかる。 |
適した成育環境 | 日向が最適だが、半日陰程度でも耐えられる。 |
年間の剪定回数と時期 | 剪定は真夏を除けばいつでも可能。剪定をサボると下の方の枝がなくなりやすい。 |
耐病性と理由 | 病害虫に強い。 |
ブラシノキ

項目 | 内容 |
特徴 | ブラシノキは、常緑の低木で、高さは1m程度。葉は対生し、長さは約5cm、幅は約2cmで、先端は尖っています。葉の表面は濃緑色で光沢があり、裏面は灰白色です。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は5月から6月です。観賞用として人気。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 果実をつけます。果実は長さ約1cmの楕円形で、初めは緑色ですが、熟すと黒色になります。果実の熟す時期は10月から11月です。観賞用としては向かない。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があります。寒さに強く、日本全国で栽培できます。また、日陰にも強いです。 |
成長速度 | 成長速度はやや遅いです。 |
適した成育環境 | 日なたを好みます。花を咲かせたい場合は日なたに植栽し、水はけの良い状態にしておく。い陰でも育つが花付きが悪くなる。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可ではあるが、基本的には間引いたり、切り戻し剪定がおすすめ。3月頃に剪定が可能だが、6月~7月頃の花が終わるころに行うと、翌年も花を多くつける。 |
耐病性と理由 | 耐病性は高い。 |
カラタネオガタマ

項目 | 内容 |
特徴 | 中国南部福建省及び広東省を原産とするモクレン科の常緑樹。日本へ渡来したのは江戸時代中期~明治初期で暖地の庭園や神社に植栽される。花には熟したバナナに似た香りがあり、英語ではバナナブッシュと呼ばれる。 |
開花の有無と時期 | 開花は5月~6月。花の直径は2~4センチほど。 |
常緑か落葉か | 常緑樹。 |
果実の有無と時期 | 果実はモクレンやコブシに似ており、10~11月に熟すと自然に裂けて朱色の種子が顔を出す。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さにやや弱く、特に冬の乾いた寒風を嫌う。地植えは関東以南の太平洋側が無難。 |
成長速度 | 成長は遅めで、樹形は自然に整いやすい。 |
適した成育環境 | やや湿り気のある半日陰の場所が最適。日当たりの良い場所でもよく育つ。 |
年間の剪定回数と時期 | 年に一回程度は内部の混み入った枝葉を整理した方がよい。剪定時期は開花直後の6月。 |
耐病性と理由 | 風通しや採光が悪くなるとカイガラムシやテッポウムシが発生する。しかし、一般的には病害虫の被害は少ない。 |
チャイニーズホーリー

項目 | 内容 |
特徴 | チャイニーズホーリーは、イヌツゲ科の常緑低木で、高さは1-2mになります。白い小花を咲かせますが、クリスマスの定番として使われる、赤い実が成ることでとても人気です。 |
開花の有無と時期 | 春に小花を咲かせます。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 秋もしくは冬に赤い実をつけます。 |
耐候性の有無と理由 | 耐寒性があり、寒さに強いです。しかし、強い日差しは苦手なので、半日陰の場所が適しています。 |
成長速度 | 成長速度はやや遅いです。 |
適した成育環境 | 半日陰の場所が適しています。また、水はけの良い土壌を好みます。 |
年間の剪定回数と時期 | 年に1回、春に剪定を行います。 |
耐病性と理由 | 病気に強い。 |
ユキヤナギ

カテゴリ | 詳細 |
特徴 | ユキヤナギは、落葉高木で、高さは10m程度に成長します。冬季に白い花を咲かせることからユキヤナギ(雪柳)と呼ばれます。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は3月から4月にかけて白い花を咲かせます。 |
常緑か落葉か | 落葉低木です。 |
耐候性の有無と理由 | 耐寒性は強く、寒い場所でも育つ。 |
成長速度 | 成長速度は速い |
適した成育環境 | ユキヤナギは日当たりの良い場所を好みます。半日陰でも、ある程度花は咲く。 |
年間の剪定回数と時期 | 刈り込み可。剪定は、花が終わった春に行います。剪定により、より多くの花を咲かせることができます。 |
耐病性と理由 | 病気には強いが、うどんこ病やカイガラムシには注意が必要。 |
ハーブ系の植物 ローズマリー(木立性)

カテゴリ | 詳細 |
特徴 | ローズマリーは、乾燥した岩場の地中海地域原産の香りの良いハーブで、装飾的、薬用、料理用、そして視覚的な庭の魅力のために一般的に栽培されています。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は10月~5月にかけてで、花色は主に青から紫ですが、ピンクや白の花を咲かせる品種もあります。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
耐候性の有無と理由 | ローズマリーは耐候性があり、乾燥に強く、塩分にも耐性があります。しかし、非常に寒冷な気候には弱いため、冬季には屋内に移動することを検討する必要があります。 |
成長速度 | 成長速度は中程度です。 |
適した成育環境 | ローズマリーは、日当たりの良い場所と、水はけの良い土壌を好みます。半日陰でも育つ。 |
年間の剪定回数と時期 | 定期的に剪定することで、茂みを形成し、長くなりすぎるのを防ぎ、新しい葉の成長を促します。剪定は春に行うことが一般的です。 |
耐病性と理由 | ローズマリーは比較的病害虫に強い植物ですが、乾燥した暑い状況ではスパイダーマイト、湿度の高い環境ではうどん粉病が発生する可能性があります。 |
【目隠しとしても使える】人気の植木
| 樹種名 | タイプ | 成長速度 | 推奨剪定回数 | 特徴 | 注意点 |
| オリーブ | 常緑樹 | 速い | 年1回(冬) | ・銀色の葉がおしゃれで洋風の庭に合う ・実を収穫して楽しめる | ・日当たりの良い場所を好む ・剪定方法に少しコツがいる |
| エゴノキ | 落葉高木 | 速い | 年1回(冬) | ・春に咲く白い花が美しい ・自然な樹形が楽しめる | ・実の皮に毒がある ・乾燥に弱く、西日に注意が必要 |
| ハイノキ | 常緑樹 | 遅い | 年1回(早春) | ・涼しげな小さな葉が特徴 ・病害虫に比較的強い | ・耐寒性がやや弱く、暖地での植栽向き ・半日陰で育てるのがベスト |
| ソヨゴ | 常緑樹 | 遅い | (ほぼ不要) | ・雌株は秋に赤い実をつける ・成長が遅く、手入れが楽で初心者向き | ・強い日差しや西日が苦手 ・剪定にやや弱い |
オリーブ

項目 | 詳細 |
特徴 | オリーブの木は、特に高温と日照が豊富な地域に適しています。銀色の葉を持ち、他の植物との組み合わせにも美しく映えます。また、オリーブの実はオイルを抽出するためにプレスされたり、塩漬けにして食べられたりします。 |
開花の有無と時期 | 開花します。5月~6月上旬に開花する。鑑賞用ではない。 |
常緑か落葉か | 常緑です。 |
果実の有無と時期 | 果実(オリーブ)をつけます。オリーブの木は約3年で成熟し、顕著な量の果実をつけ始めます。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性があります。特に、暑く乾燥した地域でよく育ちます。耐寒性もあり、寒さにも耐える。 |
成長速度 | 成長速度は速い。 |
適した成育環境 | オリーブの木は、よく排水された土壌と日当たりの良い場所を好みます。日当たりの悪い場所でも育つが、日当たりの良い場所の方が良く育つ。 |
年間の剪定回数と時期 | 年1回、冬に剪定するとよい。強剪定は2月か3月、間引く剪定は3月か4月に行うとよい。 |
耐病性と理由 | 耐病性も優れていて育てやすい。 |
エゴノキ

項目 | 内容 |
特徴 | 日本や中国、朝鮮半島の山野や庭園などに見られる落葉高木。春先に花が咲く。葉が小さいので、コじゃれたお庭にしたい方はおすすめ。 |
開花の有無と時期 | 開花あり。開花期は5月ごろ。直径2~2.5cm程度の小さな白い花を枝から下げるように咲かせる。 |
常緑か落葉か | 落葉高木 |
果実の有無と時期 | 果実あり。秋に実る。実の皮が有毒で、食べると「えぐい」ことからエゴノキと名がつきました。 |
耐候性の有無と理由 | 耐候性あり。適地に植えれば丈夫です。ただし、乾燥は苦手なので、西日の強いところで管理したりすると、葉が乾燥して反り返ったりすることもあります。 |
成長速度 | 成長速度は速い |
適した成育環境 | 日光を好みます。とはいえ、半日陰程度なら、難なく十分に育つことができます。ただし、日光に当てるのと当てないのとでは、花の付き方も大きく変わってくるので、きれいな花を咲かせたい人は、できるかぎり日光の当たる場所で育てることをおすすめします。 |
年間の剪定回数と時期 | 11月~12月か2~3月が適期です。横に枝をはる自然な樹形が楽しめる樹木なので、不要な枝だけを間引く程度の剪定でかまいません。伸びすぎている枝や上下に向いている枝、混み合っている枝を付け根から切り取っていきましょう。 |
耐病性と理由 | 耐病性は強いと言われていますが、害虫の被害に合う可能性も高いので、消毒を行い、害虫が寄り付かないようにしておくと、元気に育つ。 |
ハイノキ

項目 | 内容 |
特徴 | ハイノキは、カキノ目ハイノキ科ハイノキ属の常緑樹で、さらさらっとした小さな葉っぱがが涼しさを演出します。 |
開花の有無と時期 | 開花します。開花時期は春(4月から5月)す。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | 果実は球形で、秋(9月から10月)に熟します。 |
耐候性の有無と理由 | 耐寒性はやや弱い。霜に当たると傷む。原産地が近畿地方より西側の温かい地方の暖地に生える気なので、暖地での植栽が向いている。 |
成長速度 | 成長速度は遅い。 |
適した成育環境 | 基本的には、半日陰で植える事がベスト。日なたでも育つが、葉つきが悪くなったり、葉っぱが黄色くなる事もある。 |
年間の剪定回数と時期 | 年に1回、新芽が出る前の早春に剪定します。 |
耐病性と理由 | ハイノキは比較的、病害虫に強いとされています。 |
ソヨゴ

項目 | 内容 |
特徴 | 関東地方以西の本州、四国、九州を原産とするモチノキ科の常緑樹。成長速度も遅く、初心者でも手入れが楽な植木。 |
開花の有無と時期 | あり。6~7月頃に小さな目立たない花を咲かせる。 |
常緑か落葉か | 常緑 |
果実の有無と時期 | あり。ただしソヨゴには雄と雌があり、雌株のみ実が成る。雌花の後に直径5mmほどの果実ができ、10~11月に赤から黒に熟す。 |
耐候性の有無と理由 | 寒さには比較的強いが、関東地方でも環境が悪いと葉が貧弱になる。 |
成長速度 | 成長は遅い。 |
適した成育環境 | 日当たりを好むが、強い日差しは苦手で、特に夏の西日を嫌う。半日陰地で育てた方が葉色はよくなる。 |
年間の剪定回数と時期 | 剪定にやや弱い。2月頃の剪定がおすすめ。剪定には弱いが、成長速度が遅いので、それほど剪定をする必要がなり。しばらく放置して、枝葉が混み入ってきたら、透かし剪定や間引く剪定を行う。 |
耐病性と理由 | 病害虫には比較的強い。 |
【要注意】生垣でおすすめしない植木の種類
これまでに、生け垣の手入れを不要にする代用品をお伝えしましたが、「そうは言っても生垣も捨てがたい」という人もおられる事かと思います。
そこで生垣を検討する上で、手入れ以外にもに注意しないといけないことがあります。
それは、生垣で一般的に使われる植物の中には、てがつけられないほど巨大になる植木があるという事です。
他にも、葉が多く落ちる樹種、旺盛に成長しすぐに剪定が必要な植物、そして害虫が寄り付きやすいもの…。
適切な選択をしないと、想像以上の手間とストレスが待っています。
そこで次に、生垣選びの際に避けたほうがよい植物の種類とその理由について詳しく解説します。
※ここでご紹介する生垣は、あくまで私達の経験上「植えない方が良い」というものであり、植物自体を否定するものではございません。
| 樹種名 | タイプ | おすすめしない主な理由 | 具体的なリスク |
| シラカシ | 常緑高木 | 非常に早い成長スピード | ・あっという間に高くなり、頻繁な剪定が必須になる ・枝葉が密集し、虫が寄り付きやすい ・落葉の掃除が手間になる |
| コニファー類 | 常緑針葉樹 | 驚くほどの成長スピード | ・放置すると、手に負えないほどの大きさになる ・定期的な剪定に多くの時間と労力が必要になる |
| カイズカイブキ | 常緑針葉樹 | 強い成長力で巨大化する | ・放置すると家の高さを超え、管理が非常に大変になる ・横にも広がりやすく、通行の妨げになることがある |
| シマトネ-リコ | 常緑高木 | 成長が早く、根が強力 | ・あっという間に巨大化し、自分で手入れができなくなる ・強力な根が排水マスなどに侵入し、詰まりの原因となる |
シラカシ
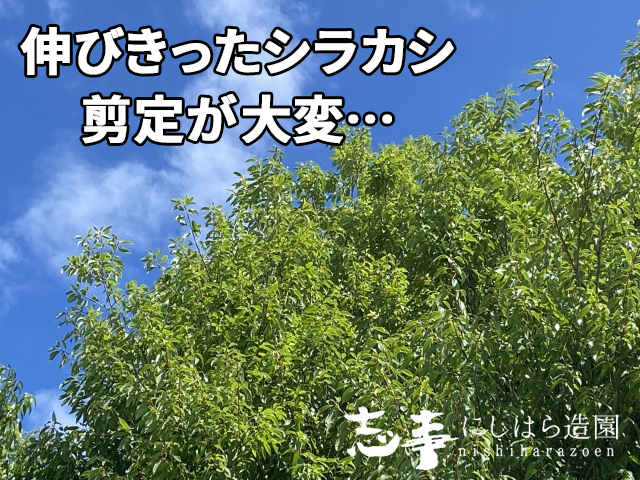
シラカシはその名の通り、まっすぐに高く成長する特性を持つ樹種です。この特性が、私たち造園屋から見て生垣として適さない理由となっています。
なぜなら、シラカシの旺盛な成長力が、そのまま手入れの頻度と手間を増やすからです。
具体的には、シラカシは成長スピードが非常に速く、あっという間に高さを伸ばします。
そのため、生垣としての形を保つためには定期的な剪定が欠かせません。
また、シラカシの枝と葉は密集する傾向にあり、これが虫が寄り付きやすい環境を作ります。
これはハチや鳥が巣を作る可能性を高め、虫などが嫌いな方にとっては非常に不快な思いをする原因ともなります。
また、シラカシは葉を落とすため、その掃除がまた別の手間となります。植えたは良いものの、想像以上のメンテナンスに追われる結果となることは避けたいですよね。
以上の理由から、シラカシは生垣としては手入れが大変であるため、おすすめできません。より管理が楽で、美しい生垣を保つためには他の樹種を選択することをお勧めします。
コニファー類

まずは結論からお伝えすると、生垣としてコニファーを選ぶことは慎重になった方が良いでしょう。
その主な理由は、コニファー類全体的に言えることですが、コニファーの成長力の強さにより、管理が難しくなる可能性があるからです。
コニファーは、美しい針葉を持ち、その姿は生垣として魅力的に映るかもしれません。
しかしその裏側では、放置してしまうと驚くほどのスピードで成長を続け、いつの間にか手に負えないほどの大きさになってしまうのです。
例えば、ある日窓から庭を見ると、コニファーがあっという間に家の高さを超えているなんてことは、想像より現実的な出来事となります。
そのため、定期的に剪定を行う必要があり、これは予想外の時間と労力を必要とする可能性があります。
つまり、その生育力の強さから、生垣としてコニファーを選ぶことは、特に管理が難しくなる可能性があるため、おすすめできません。
その美しさを楽しみつつ、手間を掛けずに管理することが可能な他の樹種を選ぶことをお勧めします。
カイズカイブキ

生垣としてカイズカイブキを選択することも止めておいた方が良いでしょう。
その理由として、カイズカイブキは強い生長力を持ち、手入れを怠ると巨大な大きさに育ってしまうからです。
カイズカイブキは生垣として古来から人気がありますが、その成長力は非常に強く、放置しておくと驚くほどの高さに育ちます。
酷い場合、家の高さを越え、周囲に広がる姿は見応えがある一方で、その管理は大変な労力を必要とします。
また、頻繁な剪定が必要となり、それを怠ると歩道を覆うほどに横に広がり、通行人の迷惑になることもあります。
さらに、巨大になると素人が剪定を行うには手に負えなくなるため、専門的な道具や技術が必要となります。
また、巨大になれば伐採を行う費用も掛かります。
上記のような事から、生垣としてカイズカイブキを選ぶことは、その強い生長力とそれに伴う手間から、おすすめできません。
代わりに、手入れが容易で、適度な大きさを保つ樹種を選ぶことをお勧めします。
シマトネリコ
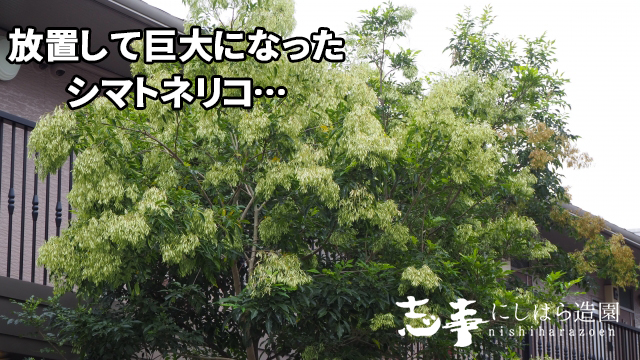
シマトネリコは生垣として使われることはないでしょうが、お勧めしない植木の代表格なのでお伝えしておきます。
まず結論から言うと、シマトネリコをお勧めしない理由は、成長が早く、手入れを怠ると知らない間に家の高さを超えてしまうからです。
例えば、何も手を加えずに放っておくと、シマトネリコはあっという間に大きくなり、自分で手入れができないくらい、巨大になってしまいます。
また、シマトネリコの根は強力で広範囲に広がる特性があります。
そのため、雨水マスや汚水マスに侵入し、目詰まりを起こす可能性があります。特に汚水に侵入して目詰まりを起こした場合なんて最悪です。お風呂の排水どころか、トイレの汚物まで詰まらせてしまうので。
特にやってはいけないのが、汚水桝や雨水桝の近くにシマトネリコを植えてしまう事です。根っこが水を求めて枡の中に侵入していくからです。
したがって、上記の理由から、シマトネリコを植える事はおすすめできません。
成長速度の制御と根の問題を適切に管理できる方でない限り、他の樹種を選択した方が良いでしょう。
もっと楽に!生垣のメンテナンス術と簡単な剪定のコツ
コツ1:電気バリカンを使用する
生垣のお手入れを楽にするためには、電気バリカンを使用することがおすすめです。
理由は、電気バリカンを使用することで、手作業での剪定に比べて労力を大幅に減らすことができ、また、均一に刈り込むことが容易になるからです。
例えば、大きな生垣を均一に刈り込む作業は、手作業では時間も労力もかかりますが、電気バリカンを使用すれば、その作業を効率的に、そして短時間で行うことができます。
結論として、生垣のお手入れを楽にするためには、電気バリカンを使用することがおすすめです。これにより、生垣のメンテナンスが簡単になり、美しい庭を維持することができます。
コツ2:秋ごろに刈り込む
生垣のお手入れを楽にするためには、秋ごろに刈り込むことがおすすめです。
理由は、秋になると植物の成長が遅くなり、その結果、次に刈り込むまでの間隔を長くすることができるからです。
例えば、春に刈り込むと、その後の成長期に急速に生長してしまい、頻繁に手入れが必要になります。
しかし、秋に刈り込むと、冬の間は成長が遅く、春まで刈り込む必要がなくなります。
結論として、生垣のお手入れを楽にするためには、秋ごろに刈り込むことがおすすめです。これにより、手間を減らし、生垣の管理がより簡単になります。
コツ3:消毒を行う
生垣のお手入れを楽にするためには、定期的に消毒を行うことが大切です。理由は、消毒を行うことで病気や害虫の発生を抑え、生垣の健康を保つことができるからです。
例えば、剪定後の傷口は病気や害虫の侵入口となりやすいのですが、消毒を行うことでこれらのリスクを減らすことができます。
また、定期的に消毒を行うことで、早期に病気や害虫を発見し、対処することも可能になります。
結論として、生垣のお手入れを楽にするためには、定期的な消毒が重要です。これにより、生垣の健康を保ち、長期的に見て手入れの手間を減らすことができますよ。
コツ4:防草シートを利用する
生垣の下に防草シートを敷くことで、雑草の発生を防ぎ、管理も楽になります。防草シートは、水は通すので、生け垣への悪影響などはありません。
DIY?業者依頼?費用と手間の境界線をプロが解説
生垣のリフォームや新しい目隠しの設置方法が決まったら、次に考えるのは「これを自分でやるか、プロに頼むか」という問題ですよね。
費用を抑えたいDIY志向のご家庭もあれば、時間や体力、仕上がりの品質を考えて業者に任せたいという方もいらっしゃいます。
ここでは、2000件以上の現場を経験してきた私の視点から、「どこまでがDIYで可能か」「どこからがプロに任せるべきか」という具体的な境界線と、それぞれの費用感を分かりやすく解説します。
ここまではDIY可能!費用を抑えるポイント
少しでも費用を抑えたいと考えた時、DIYは非常に有効な選択肢です。私の経験上、一般的に「植えるだけ・外すだけ」といった、重機や特殊な基礎工事を必要としない作業はDIYに向いています。
例えば、高さ1m以下の苗木を数本植えるだけの小規模な生垣づくりや、市販のキットを使ったラティスフェンスの設置などがこれにあたります。
特に、結束バンドなどで固定するだけのフェイクグリーンの取り付けは非常に簡単なので、DIYを推奨します 。DIYであれば、業者に頼む場合の工事費(例えば10mで約3〜4万円)を節約できます 。また、生垣の枝葉部分だけ自分で切り払ってゴミ処分し、最も大変な抜根だけをプロに任せるという「部分的DIY」も、費用を抑える賢い方法です 。
ただし、DIYで最も注意すべきは安全と品質です。特にラティスなどは、支柱の固定が甘いと強風で倒壊する危険があります 。無理だと思ったら、途中からでもプロに相談する勇気を持ってくださいね。
プロに任せるべき作業と費用相場
一方で、安全や品質、将来的なトラブル防止の観点から、プロに任せるべき作業も明確に存在します。特に、「重労働・特殊技術・法規」が関わる領域は、専門家の出番です。代表的なのは、長年育った生垣の抜根(根こそぎ撤去する作業)です 。
地中に深く張った根を素人が完全に取り除くのは非常に困難で、中途半端に残すとシロアリの発生源になったり、新しいフェンスの基礎工事の邪魔になったりします 。
また、高さのあるブロック塀やフェンスの設置もプロに任せるべきです。これらは構造物であり、建築基準法で高さ2.2m以下などの規定があるほか 、地震や台風で倒壊しないための頑丈な基礎工事が不可欠だからです。
費用はかかりますが、これは安全への投資と考えるべきでしょう。費用の目安として、生垣の撤去は1mあたり1万〜3万円 、目隠しフェンスの設置は1mあたり1.5万〜4万円 、ブロック塀なら1mあたり1万〜3万円 ほどを見ておくと良いでしょう。
これらの作業は、単に費用が浮くからとDIYで行うにはリスクが高すぎます。安全で確実な施工のためにも、専門業者に相談することを強くおすすめします。
生垣の手入れを不要にしたいけど、どうしたらいいか分からなくない人へ
奈良県にお住いの方へ
あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?
「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」
「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」
そう思っていませんか?
そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、
「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」
「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」
「結局、工事金額はいくらかかるの?」
そう思っていませんか?
これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。
そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料相談」がお役に立てるかもしれません。
毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。
今月はあと5名
お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休
まとめ:後悔しないために、あなたの「最優先」を決めましょう
今回は、「生垣の手入れを不要にしたい」という切実な悩みについて、解決策を詳しく解説してきました。長年の負担から解放される道筋は、見えてきましたでしょうか。
この記事で最もお伝えしたかったのは、解決策は一つではないということです。あなたの状況に合わせて、大きく2つの道があります。一つは、「生垣そのものをやめて、フェンスなどの代替案に切り替える」という道。これは、安全性や将来の時間的余裕を最優先したい方に最適な選択です。
もう一つは、「手間のかからない樹種を選んで、生垣を続ける」という道。こちらは、やはり緑のある暮らしを諦めたくない、という方に向けた選択肢です。その際は、目隠し機能を重視するのか、あるいは剪定や掃除の手間を極限まで減らすことを重視するのか、ご自身の価値観と向き合う必要があります。
どちらの道を選ぶにせよ、大切なのは「5年後、10年後のご自身の暮らし」を想像してみることです。もし、ご自身の状況でどちらが最適か判断に迷う場合は、ぜひ一度、私たちのような専門家にご相談ください。奈良県内であれば、私が直接お話を伺い、あなたの暮らしに寄り添った最適なプランを一緒に考えさせていただきます。