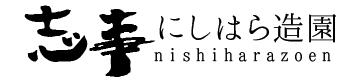庭の苔の除去でお悩みではありませんか?取っても取ってもキリがない、しつこい庭の苔。
これまでにホームセンターで評判の薬剤を試したり、汗だくになって高圧洗浄機をかけたりしても、翌年には元通り。それどころか、「去年より苔の範囲が広がってないか…」なんて虚しい気持ちになってしまうことはありませんか。
苔の原因は単なる湿気だけでなく、多くの場合、土の中の「見えない水」や水はけの悪さといった根本的な原因が隠れています。
そこでこの記事では、奈良県で多くの造園工事を手掛けてきたプロの視点から、苔が発生する本当のプロセス、場所別の正しい応急処置、そして苔の再発を防ぐための根本的な排水対策まで、実際の事例と合わせて詳しく解説していきます。
この記事で得られる内容
- 庭の苔を放置する危険性(転倒リスク・美観)
- DIYでできる5つの応急処置(薬剤・高圧洗浄・熱湯など)
- 場所別(芝生・コンクリート・土)の正しい苔の落とし方
- 苔が再発する本当の原因(日陰・土質・排水)
- プロが実践する根本的な再発防止策(土壌改良・暗渠排水)
- DIYと業者依頼の判断基準、費用相場

西原 智(西原造園 代表)
奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人
奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。
職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。
これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。
本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。
全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。
庭の苔の除去と対策で悩まれていた奈良県のY様の事例

今回ご紹介するのは、私たち西原造園にご相談くださった奈良市にお住まいのY様邸のケースです。
Y様が長年心を痛めていたのが、ご自宅の裏庭を覆うしつこい苔の問題でした。雑草はなんとかご自身で抜くことができても、地面にびっしりと張り付いた苔だけは、ほぼ何もできない状態だったと言います。
Y様もこの状況をなんとかしようと、一度はご自身での対策を考えられました。しかし、目の前に広がる苔を前に、「これは自分ではどうにもならない」と途方に暮れてしまったそうです。
「草は抜けるけど、苔だけはどうにもならない…」。
お庭は日当たりも悪く、雨が降るたびにぬかるんでドロドロに。お子様が外で遊ぶことも難しい状態でした。いつしかお庭は安らぎの場所ではなく、見るたびに「はぁー…」とため息が出てしまう、悩みの種になっていたのです。
このままではいけないとご自身での対策に限界を感じたY様は、インターネットで専門家を探し、私たちのホームページをご覧いただきました。「どういう工事をするのかが具体的に書かれていて分かりやすかった」と、無料相談にお声がけくださったのが始まりです。
Y様の最終的なご要望は、この苔とぬかるみの問題を根本から解決し、「人工芝にすることで、子どもが安心して走り回れる庭をつくりたい」というものでした。
庭の苔を放置する3つのデメリット・危険性

お庭の苔は、見た目が悪いだけでなく、ご家族の生活にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。特に「滑る」といった安全面での問題や、大切に育てている他のお花や芝生への影響は深刻です。放置することでどのようなデメリットがあるのか、具体的に見ていきましょう。
1. 滑って転倒する
苔の最も怖いデメリットは、滑って転倒するリスクです。苔や藻類は、雨で濡れると表面に水の膜ができ、非常に滑りやすくなります。特に玄関アプローチや駐車場のコンクリート、タイルに繁殖すると、靴底との摩擦が大幅に低下し、まるで氷の上を歩くようになることもあります。
実際に「家族が苔で転んでしまった」「ヒヤリとした」というお話はよく伺います。特に小さなお子様や、足腰の弱いご高齢の方が苔で滑ると、骨折など重傷につながる危険性が高いです。ご家族の安全を守るためにも、苔は「滑る前」に除去することが肝心です。
2. 家の美観を損ねる
せっかくのお庭や外構も、苔が広がると台無しになってしまいますよね。コンクリートやブロック塀が真っ黒・緑色に変色し、家全体が古びた印象になってしまいます。この見た目の悪化は、「家が汚い」「手入れ不足」と映るため、大きな精神的ストレスとなります。
「また生えてきた…」と庭を見るたびに憂鬱になり、住まいへの愛着も低下しかねません。苔はカビと共生することも多く、黒ずんだ汚れは不衛生な印象を与えます。日々の暮らしの満足度を下げる要因にもなるため、美観を保つためにも早めの対策が必要です。
3. 芝生や他の植物の生育を阻害する?
芝生やガーデニングを楽しまれている方にとって、苔は厄介な存在です。苔自体が植物に直接毒を出すわけではありませんが、間接的に生育を阻害します。特にゼニゴケ類は、地表を絨毯(じゅうたん)のようにびっしりと覆ってしまいます。
これにより、下の芝生に日光が当たらなくなったり、空気の通りが悪くなったりします。水や養分も苔に奪われがちになり、結果として芝生が弱って部分的に枯れたり、薄くなったりする原因になります。また、湿った苔の環境は病害虫の温床にもなりやすいため、他の植物を守るためにも除去が推奨されます。
庭の苔を除去する5つの「応急処置」方法
今まさに目の前にある苔をなんとかしたい、という場合、まずはご自身でできる「応急処置」が基本になります。
薬剤、高圧洗浄機、身近なものを使った方法など、いくつか選択肢があります。これらは根本解決ではありませんが、苔をリセットするために重要です。それぞれの特徴や手間、安全性を比較してみましょう。
| 方法 | 手軽さ(労力) | 即効性 | コスト目安 | 主な対象場所 |
| 1. 薬剤 | ◎ (撒くだけ) | △ (数日待つ) | 数百円~数千円 | 全般 (薬剤による) |
| 2. 高圧洗浄機 | 〇 (機械力で楽) | ◎ (即時) | 数千円~ (レンタル/購入) | コンクリート・外壁 |
| 3. 石灰/熱湯/重曹/酢 | 〇 (手軽) | △ (ムラあり) | ~数百円 | 小面積・薄い苔 |
| 4. 物理除去 | × (重労働) | ◎ (即時) | ほぼ0円 | 全般 (だが再発しやすい) |
| 5. 業者依頼 | ◎ (依頼のみ) | ◎ (施工日) | 数万円~ | 全般・根本原因 |
1. 薬剤(苔除去剤・除草剤)で苔を除去する

市販の苔除去剤は、撒いて待つだけなので労力が少なく、手軽に応急処置をしたい方に向いています。苔の細胞を破壊する成分が含まれており、散布後数日で苔が茶色く枯れ、剥がれやすくなります。
ただし、薬剤選びには注意が必要です。特に芝生のあるお庭では、「芝生用」「コケ専用」と明記された選択制の薬剤を選ばないと、芝生ごと枯らしてしまう恐れがあります。
また、散布する際は晴れた風のない日を選び、ペットや小さなお子様がいるご家庭では、散布当日はその場所に立ち入らせないといった配慮が不可欠です。
2. 高圧洗浄機で苔を洗浄・洗い流す(※コンクリートに推奨)

駐車場のコンクリートや玄関アプローチ、外壁など、硬い素材の苔除去には、高圧洗浄機が最もスピーディーで確実です。
デッキブラシで擦るより短時間で、苔を根こそぎ吹き飛ばすことができます。黒ずんだ土間コンクリートが、見違えるように明るくなることも多いですね。
ただし、注意点もあります。水圧が強すぎるため、芝生の中や土の地面には使えません。
また、対象物にノズルを近づけすぎると、コンクリートの表面を削ってしまったり、外壁の塗装を剥がしてしまったりする恐れがあります。適切な距離を保ち、周囲への泥水の飛散にも注意しながら作業する必要があります。
3. 熱湯・重曹・酢など身近なもので苔を除去する

薬剤を使いたくない、という方には、ご家庭にあるもので対処する方法もあります。熱湯は、苔が高温に弱い性質を利用したもので、45℃以上のお湯でダメージを与えられます。小規模な苔には手軽ですが、広範囲には手間がかかり、火傷にも注意が必要です。
重曹は弱アルカリ性で苔の細胞膜を壊す作用があり、コンクリート面の薄い苔に使えますが、効果は弱めです。土壌に撒くと他の植物も枯らすリスクがあります。
酢は強酸性で苔を枯死させますが、厚い苔には効きにくく、金属にかかると錆びの原因になるため、使う場所を選びます。これらはあくまで補助的な手段と考えるのが良いでしょう。
4. ブラシやスコップで物理的に苔を取り除く(※限界あり)

最も原始的ですが、薬剤を使わずに今すぐ綺麗にできるのが、手作業による物理除去です。コンクリートならワイヤーブラシで擦り、土の上ならスコップで表土ごと削り取ります。芝生の中なら熊手で掻き出す方法もあります。
この方法の最大のデメリットは、労力が非常に大きいことと、再発しやすいことです。特にブラシで擦る場合、苔の根(仮根)や胞子を取り残しがちで、すぐにまた生えてきてしまいます。
広範囲になればなるほど重労働ですし、苔が生えた根本原因(湿気や土壌)は何も解決していません。あくまで一時的な措置と割り切る必要がありますね。
5. 専門業者に「根本解決」を依頼する
「DIYでは範囲が広すぎる」「何度取っても再発してキリがない」という場合は、私たちのような専門業者に依頼するのも一つの選択肢です。プロに任せる最大のメリットは、苔を除去するだけでなく、苔が発生する根本原因を診断し、解決策を提案できる点にあります。
例えば、単に高圧洗浄するだけでなく、土壌の水はけが悪いなら土の入れ替えや暗渠排水工事、日当たりが悪いなら剪定など、総合的な対策が可能です。
もちろん費用はDIYよりかかりますが(簡易清掃で数万円~、根本工事なら数十万円規模)、苔掃除のストレスから解放され、長期的な安心を得られるのは大きな価値だと思います。
【場所別】庭の苔の正しい除去方法・落とし方(応急処置編)
ひとくちに「庭の苔」と言っても、生えている場所の素材によって、最適な除去方法は異なります。
芝生に使える方法をコンクリートでやっても効きにくかったり、逆にコンクリート用の強力な方法を芝生で使うと枯れてしまったりします。場所ごとの正しい「応急処置」を見ていきましょう。
1. 芝生の苔を除去する方法
大切に育てている芝生の苔対策は、最も慎重さが求められる場所ですね。ここで強力な非選択性の除草剤を使ってしまうと、芝生ごと全滅してしまいます。
芝生の苔を除去する場合は、必ず「芝生用」と明記された選択制の苔除去剤を選んでください。例えば「キレダー水和剤」などは、プロの現場でも使われ、芝生を枯らさずに苔だけを退治できる薬剤の一つです。
薬剤を使いたくない場合は、熊手やレーキで物理的に苔を掻き出す方法もあります。
苔を取り除いた後は、芝生が根を張りやすくするために目土(めつち)や目砂(めすな)を薄く入れておくと、苔の再発防止にもつながります。その後、適切な肥料を与えて芝生自体を健康に育て、苔に負けない強い芝にすることも重要です。
2. 駐車場のコンクリートの苔や藻を除去する落とし方
駐車場の土間コンクリートに広がった黒苔や藻は、高圧洗浄機を使うのが最も効率的です。私たちプロの現場でも、まず高圧洗浄機で大まかな苔を吹き飛ばします。
さらに頑固な黒ずみには、塩素系漂白剤(ハイターなど)を薄めてスプレーし、数分置いてからブラシでこすると驚くほど綺麗に落ちることがあります。
ただし、ここで絶対にやってはいけないのが、サンポールなどの「酸性洗剤」を使うこと。コンクリートはアルカリ性なので、酸で表面が溶けてしまい、かえって劣化を早め、汚れやすいザラザラな状態にしてしまいます。
3. 土・地面の苔を除去する方法と対策
庭の土や地面、特に日陰の部分に広がる苔は、正直なところ最も再発しやすい厄介な場所です。
応急処置としては、スコップで苔が生えている表土ごと数センチ削り取るのが手っ取り早いです。削り取った部分には、新しい土や川砂などを入れておくと良いでしょう。
広範囲の場合は苔用の除草剤を散布する方法もありますが、土壌の湿気や酸性度といった根本原因が変わらない限り、またすぐに生えてきてしまいます。
そのため、土の地面の苔対策は、応急処置と同時に、後述する土壌改良(石灰を撒いてpHを調整する、砂を混ぜて水はけを良くする)や、排水対策をセットで考えることが不可欠です。
4. 砂利・白玉砂利の苔を除去する方法
砂利、特に白玉砂利が緑色になってしまうと、とても目立ちますよね。砂利に生えた苔は、石自体に付着しているため、除去が少し面倒です。範囲が狭ければ、苔の付いた石を手で拾ってブラシでこするか、いっそ新しい砂利と交換してしまうのが早いです。
広範囲の場合、砂利を一度集めて高圧洗浄機で洗うか、バケツなどに入れて水洗いする方法もありますが、大変な労力がかかります。
薬剤を上から撒く方法もありますが、石の隙間まで浸透しにくく、効果が出にくい場合もあります。
砂利敷きの場合は、苔が生える前に、下に敷いた防草シートが破れていないかをチェックし、定期的に砂利をかき混ぜて日光に当て、乾燥させることが予防につながります。
5. 外壁・ブロック塀の苔の落とし方
家の北側やブロック塀は、日当たりが悪く湿気がこもりやすいため、苔の定番スポットです。手の届く範囲であれば、高圧洗浄機で洗い流すのが最も早いでしょう。
ただし、外壁の塗装が古い場合、高圧で塗膜ごと剥がしてしまう恐れがあるため注意が必要です。
高圧洗浄機がない場合や、素材を傷めそうな場合は、塩素系漂白剤(カビキラーなど)を吹き付けて苔を分解し、しばらく置いてからブラシでこすり、水で洗い流す方法も有効です。
ただし、塩素系薬剤は金属を錆びさせたり、植栽にかかると枯らしてしまったりする可能性があるため、養生(ようじょう)をしっかり行い、使用後は大量の水で洗い流すことが重要です。
【手段別】DIYでの苔除去(応急処置)の詳細
ご自身で苔の応急処置を行う場合、どの道具や薬剤を選べばよいか迷いますよね。ここでは、市販の苔除去剤の選び方から、高圧洗浄機のメリット・デメリット、そして熱湯や重曹といった身近なものの効果について、もう少し詳しく掘り下げて解説します。
| 製品名 | 主な成分 | 得意な場所 | 形状 | 特徴 |
| コケとーるシャワー | ペラルゴン酸 | コンクリ・アプローチ | シャワー (そのまま) | 食品成分由来・速効性 |
| コケとーる 原液 | 第四級アンモニウム塩 | 地面全般 (非農耕地) | 希釈タイプ | コスパ◎・苔の種類を選ばない |
| キレダー水和剤 | ACN (アクロニトリル系) | 芝生に最適 | 水和剤 (希釈) | プロも使用・芝生を枯らさない |
| コケそうじスプレー | 第四級アンモニウム塩 | 小面積・スポット(塀・タイル) | スプレー (そのまま) | イシクラゲなどにも対応 |
| コケ・カビ取り | 次亜塩素酸塩 (塩素系) | コンクリ・レンガ | スプレー (そのまま) | カビによる黒ずみも漂白 |
おすすめ苔除去剤5選|場所別の比較と選び方
苔除去剤は、成分や形状によって得意な場所が異なります。
レインボー薬品「コケとーるシャワー」
あ
シャワーノズル付きで、希釈せずそのまま広範囲に撒ける手軽さが特徴です。成分は植物由来のペラルゴン酸で、ペットや子供にも比較的安心とされます。玄関アプローチや駐車場など、平らな場所の広範囲の苔に向いています。
レインボー薬品「コケとーる しっかり原液」

水で薄めて使う濃縮タイプで、コストパフォーマンスに優れています。成分は第四級アンモニウム塩系で、様々な種類の苔に効果を発揮します。広い面積の地面の苔などに適していますが、芝生には使えません。
アグロカネショウ「ゼニゴケとり(キレダー水和剤)」

これはプロも使う芝生用の苔専用除草剤です。日本芝・西洋芝を問わず、芝生を枯らさずに苔だけを強力に枯らすことができます。芝生の中のしつこい苔に悩んでいる方には最適です。
パネフリ工業「コケそうじスプレー」

手軽なスプレータイプで、玄関タイルや塀の一部など、小面積のスポット除去に便利です。成分は第四級アンモニウム塩系で、イシクラゲなどにも効果があるとされます。
トーヤク「コケ・カビ取り」(スプレー)

こちらは次亜塩素酸塩(塩素系)を配合しており、苔と同時にカビによる黒ずみも漂白するように除去できるのが特徴です。コンクリートやレンガのしつこい黒苔・黒カビに強力ですが、塩素系なので植栽や金属部にはかからないよう注意が必要です。
選び方のポイントは、「場所」(芝生か、コンクリートか)と「範囲」(スポットか、広範囲か)で使い分けることですね。
高圧洗浄機を使う場合のメリット・デメリットと注意点
高圧洗浄機は、特にコンクリートや外壁の苔除去において非常に強力なツールです。
メリットは、何といってもそのスピードと労力軽減です。ブラシで1時間かかるような場所も、数分で綺麗にできる爽快感があります。また、基本的には水圧だけで落とすため、薬剤を使いたくないご家庭にも適しています。
一方、デメリットは、まず初期コスト(購入費やレンタル費)がかかる点です。また、作業中はモーター音が大きく、周囲への泥水の飛散が避けられません。家や窓、車などに汚れた水が飛ばないよう、養生や後片付けが必要になります。
最大の注意点は、素材を傷めるリスクがあることです。ノズルを近づけすぎると、コンクリートの表面を削ったり、外壁の塗装を剥がしたりする恐れがあります。必ず対象物から15~30cmは離し、一点に集中させず、掃くように動かしながら使うのがコツです。
石灰・重曹・熱湯・酢は本当に効果がある?場所別の向き不向き
ご家庭にあるもので対策できれば一番手軽ですよね。それぞれの向き不向きを解説します。
石灰(苦土石灰など)
これは「応急処置」ではなく「予防(土壌改良)」として使うものです。苔は酸性の土を好むため、石灰で土壌をアルカリ化すれば苔は生えにくくなります。芝生の苔対策としてpH調整に使うのは非常に有効ですが、撒いてすぐに苔が消えるわけではありません。
重曹
効果はかなり限定的です。コンクリートなどの薄い苔には多少効きますが、頑固な黒苔には力不足です。また、土の上に撒くと他の植物も枯らすリスクがあるため、おすすめしません。
熱湯
小面積では効果絶大です。苔は高温に弱く、熱湯をかけると細胞が死んで簡単に剥がせるようになります。ただし、広範囲となると大量のお湯を準備するのが非現実的です。タイル目地など、ピンポイントで使うのに向いています。
酢
食酢レベルの酸でも苔には効きますが、厚みのある苔には浸透しにくいです。また、酸はコンクリートをわずかに溶かす副作用が懸念され、金属を錆びさせるリスクもあります。
総じて、これら身近な資材はあくまで補助的、あるいはピンポイントで試す程度と考え、しつこい苔には専用薬剤や高圧洗浄機を検討するのが現実的でしょう。
| 方法 | 期待できる効果 | 向いている場所 | 注意点・向き不向き |
| 石灰 | △ (即効性なし) | 土壌のpH改善 (予防) | 応急処置には不向き。撒くと白くなる |
| 重曹 | ×~△ (効果低い) | コンクリ・ベランダの薄い苔 | 土に撒くと他の植物が枯れるリスクあり |
| 熱湯 | 〇 (小面積) | タイル目地・点在する苔 | 広範囲は非現実的。火傷に注意 |
| 酢 | △ (ムラあり) | レンガ・壁の薄い苔 | 厚い苔には効きにくい。金属を錆びさせる |
専門家が指摘する「苔が再発する」本当の原因
「掃除しても掃除しても、また苔が生えてくる…」このイタチごっこから抜け出すには、なぜ苔が再発するのか、その「本当の原因」を知る必要があります。湿気や日陰といった表面的な問題だけでなく、その土地が持つ根本的な条件が関係していることが多いんです。
原因1:日当たりや湿気(表面的な問題)
まず、苔が好む基本的な環境は、「日陰」と「湿気」です。苔は直射日光に弱いため、建物の北側や庭木の下など、日照時間が短い場所で繁殖します。
加えて、風通しが悪いと湿気がこもり、苔にとって理想的なジメジメした環境が続きます。雨が降った後、いつまでも水たまりが残っているような場所は、まさに苔の温床です。
これらは目に見える表面的な原因ですが、なぜそこが常に湿っているのか、さらに深い原因が隠れている場合があります。
原因2:土壌の質(粘土質など)
表面的な湿気の裏にあるのが、土壌の質の問題です。特に、粒子が細かく水はけが極めて悪い粘土質の土壌は、常に水分を抱え込みやすく、苔の繁殖を助長します。
粘土質の土は酸素も不足しがちで、土壌が酸性化しやすい傾向があります。苔は酸性の土壌を好むため、まさに好条件が揃ってしまいます。
また、長年手入れされず栄養が少ない痩せた土壌では、他の植物が育たず、代わりに苔だけが広がってしまうこともあります。土の質そのものが「苔体質」になっているケースは非常に多いですね。
【根本原因】土中の「見えない水」(土地の低さ・水脈)
そして、最も厄介なのが、土の中にある「見えない水」の問題です。例えば、お庭が周りの土地より少しだけ低い場合、雨水が自然と集まりやすく、地下の水位も高くなりがちです。
また、目には見えませんが、土地の中に「水脈」(みずみゃく)、つまり水の通り道ができていて、地中に常に水が滞留していることもあります。
こうなると、表面の土を入れ替えたとしても、下から常に湿気が供給されるため、苔は何度でも復活してしまいます。これこそが、何をしても苔が再発するお庭の「根本原因」であることが多いのです。
ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。
ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。
実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。
自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。
ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。
あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇
参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >
庭の苔を除去した後の「再発防止策」苔の予防方法
今ある苔を綺麗に取り除いても、苔が生えやすい環境、つまり日陰でジメジメした場所がそのままでは、残念ながら数ヶ月もすればまた元通りになってしまいます。
苔退治は、今ある症状を取り除く「対症療法」に過ぎません。本当のゴールは、苔が生えにくい庭へと体質改善する「根本解決」です。
ここでは、私たちプロが根本的な解決のために行う対策の柱と、ご家庭でもすぐに取り組める予防策をご紹介します。
根本対策1:土壌改良(砕石と真砂土に入れ替える)

苔が再発する原因として、土壌が水を抱え込みやすい粘土質であることが多い、とお話ししました。この問題を根本から解決するのが土壌改良、つまり土そのものを入れ替える方法です。これは大掛かりにはなりますが、最も効果的な対策の一つですね。
具体的には、苔が生えていた部分の湿った粘土質の土を、20~30cmほどの深さまで掘り下げて撤去します。その底に、水はけを良くするための砕石(さいせき)を5~10cmほど敷き詰め、地中の排水層とします。
その上に、土と砕石が混ざるのを防ぐ透水シート(防草シートでも代用可)を敷き、最後に水はけの良い真砂土(まさつち)や川砂を混ぜた土を入れ直して整地します。
この入れ替えによって、地面は雨が降ってもジメジメしにくい、サラサラとした乾燥しやすい土に生まれ変わります。
苔が根を張りにくい環境になるだけでなく、土壌のpHもリセットされるため、酸性の土を好む苔の繁殖を長期間抑えることができますよ。
根本対策2:暗渠排水(排水パイプを埋設し水脈を逃す)

土壌改良と並んで、水はけ問題に対する非常に強力な解決策が暗渠排水(あんきょはいすい)です。これは、先ほどお話しした「見えない水」が溜まりやすいお庭、特に土地が低い場合や水たまりがなかなか引かない場合に絶大な効果を発揮します。
具体的には、庭の土の中に穴のあいた特殊な排水パイプ(ドレーン管)を埋設し、地中にたまった余分な水を強制的に雨水桝や側溝などへ逃がしてやる工法です。
ただパイプを埋めるだけではダメで、溝を掘ったら砕石を敷き、パイプを設置し、その周りをさらに砕石で覆います。そして最も重要なのが、パイプの穴が土で目詰まりしないよう、全体を透水シートで包み込むことです。
この作業を怠ると、せっかくの暗渠がすぐに機能しなくなってしまいます。適切に施工すれば、土の中の水分量が劇的に減り、苔の再発リスクを根本から抑えることができます。
根本対策3:勾配設計(雨水桝へ水が流れる傾斜をつける)

土の中の水はけ(暗渠排水)と同時に考えたいのが、地面の表面の水の流れ、すなわち勾配(こうばい)設計です。
お庭がもし平坦すぎたり、むしろ水が溜まるように凹んでいたりすると、雨水は行き場を失い、そこに水たまりができます。これが苔の絶好の住処になってしまうんですね。
そこで、プロが整地する際は、必ず地面にわずかな傾斜をつけて、雨水が自然と雨水桝や排水口に向かって流れるように設計します。例えば、1mあたり1~2cm低くするだけでも、水はけは全く変わってきます。
表面の水がすばやく排水口へ流れてくれれば、地面が乾くスピードが格段に上がり、苔が生えにくい環境を維持できるわけです。土の中の水は「暗渠」で、表面の水は「勾配」で処理する。この両輪が大切なんですね。
(補足)DIYでできる予防策(剪定・風通し改善)
「土壌改良や暗渠排水は大事そうだけど、いきなり工事は難しい…」そう思われる方も多いですよね。もちろん、ご家庭ですぐにできる予防策もたくさんあります。これらは根本的な工事と合わせて行うと、さらに効果が高まりますよ。
- 剪定で日当たりを良くする:庭木が茂りすぎて地面が日陰になっていませんか?枝葉を剪定して光が差し込むようにするだけで、地面が乾燥しやすくなり、苔はかなり減ります。
- 風通しを良くする:物置や鉢植え、使っていない遊具などを壁際にべったり置いていませんか?少し壁から離して風の通り道を作ってあげるだけで、湿気がこもるのを防げます。
- 落ち葉掃除をこまめに:落ち葉は湿気を保つ布団のようなもの。腐葉土化すると土を酸性にもします。面倒でも、こまめに掃き掃除をして、苔のベッドを作らないことが重要です。
- 地面を覆う:裸の土をむき出しにせず、防草シートを敷いた上に砂利を敷くのが最も効果的な予防策の一つです。砂利は無機質で水はけが良く、苔が根を張れません。
庭の苔除去はDIY?業者?判断基準と費用相場
苔の対策にはご自身でできる応急処置から、私たちのような専門業者が行う根本工事まで様々です。
ここで悩ましいのが、「うちの場合はDIYで十分なのか、それとも業者に頼むべきなのか」という判断基準ですよね。費用感も含めて、プロの視点からアドバイスさせていただきます。
| 比較項目 | DIY(応急処置) | 専門業者(根本解決) |
| 費用目安 | 数百円 ~ 数万円(道具代) | 数万円 ~ 数十万円(工事内容による) |
| 作業時間・労力 | 時間と体力が必要 | 依頼するだけ(施工はプロが行う) |
| 再発のリスク | 高い (表面的な除去のため) | 低い (根本原因に対処するため) |
| おすすめな人 | ・範囲が狭い ・コストを最優先したい ・DIYの作業を楽しめる | ・範囲が広い ・何度除去しても再発する ・高齢、または忙しくて時間がない ・安全と確実性を優先したい |
DIY(応急処置)がおすすめなケース
まず、ご自身でのDIY(応急処置)がおすすめなのは、苔の範囲がまだ狭い、初期段階のケースです。
例えば、「玄関アプローチのタイル数枚が黒ずんできた」「芝生の一部に少し苔がある」といった程度であれば、市販の苔除去剤やブラシ掃除で十分対応可能です。まずはコストをかけずにご自身で試してみる価値はありますね。
また、費用を極力抑えたい場合も、まずはDIYが選択肢になります。高圧洗浄機もレンタルなら数千円で済みますし、薬剤も数千円で購入できます。
ご自身で作業する手間や時間はかかりますが、「まずは見た目だけでも綺麗にしたい」というご要望であれば、DIYで十分満足できる場合もあります。苔除去は高圧洗浄など、目に見えて綺麗になるので、DIYの達成感を味わいたい方にも向いていますね。
業者(根本解決)への依頼がおすすめなケース
一方で、私たち専門業者への依頼を強くおすすめするのは、苔の被害が広範囲・重度なケースです。
庭全体が苔に覆われている、駐車場のコンクリートが真っ黒になっている、外壁の高い所まで苔が生えている、といった場合は、DIYでは時間と労力がかかりすぎるか、そもそも安全に作業できません。
そして最も重要な判断基準は、「何度除去してもすぐに再発する」かどうかです。これは、表面的な問題ではなく、土壌や排水といった根本的な原因が隠れているサインです。
ご高齢でご自身での作業が体力的に難しい場合や、苔で滑って転倒しそうになった経験があるなど、安全面での不安が強い場合も、迷わずプロにご相談いただくのが賢明です。根本原因から解決し、長期的な安心を手に入れることができます。
業者に依頼する場合の費用相場と「正しい選び方」
業者に依頼する場合の費用ですが、あくまで目安として、苔の除去・清掃作業のみの場合、高圧洗浄などで1㎡あたり100円~300円程度からが相場感でしょうか。
ただし、外壁など高所作業で足場が必要になれば、その費用(数万~)が別途かかり、総額では3万~6万円程になることもあります。これが土壌改良や暗渠排水といった根本工事になると、お庭の広さや状況によりますが、数十万円単位の費用がかかってきます。
業者を選ぶ際は、どの業種に頼むかが重要です。単に綺麗にしたいだけならハウスクリーニング業者、外壁の苔がひどく塗装も考えているなら塗装業者、そしてお庭全体の水はけや土壌から見直したい場合は、私たちのような造園・外構業者が適任です。
必ず複数の業者から見積もりを取り、苔除去の実績はもちろん、「なぜ苔が生えるのか」という原因診断と「再発防止策」までしっかり提案してくれる、信頼できる業者を選んでくださいね。
庭の苔除去に関する注意点(やってはいけないこと)
苔の除去はご自身でも可能ですが、方法を間違えると、かえってお庭や家を傷めてしまう危険性があります。特にDIYで作業される際に、これだけは守ってほしいという「やってはいけないこと」を4点、プロの視点からお伝えします。
【重要】コンクリートに酸性洗剤(サンポールなど)は絶対に使わない
これは本当に重要なので強調させてください。駐車場のコンクリートや玄関アプローチの苔を落とすために、酸性の洗剤(例えばトイレ用のサンポールなど)を使うのは絶対にやめてください。
コンクリートはセメント由来でアルカリ性の素材です。そこに強酸性の液体をかけると、化学反応を起こして表面が溶けてしまうんです。
一時的に苔は落ちるかもしれませんが、コンクリートの表面がザラザラになり、かえって汚れや苔が付着しやすい状態になってしまいます。
劣化を早めるだけでなく、見た目にも白く変色してしまうこともあります。ネット情報などで見かけることがあっても、プロとしては決して推奨できません。コンクリートには、中性洗剤か、アルカリ性の洗浄剤(塩素系漂白剤など)を使うようにしましょう。
芝生に強力な除草剤(雑草・苔用)は使わない
芝生の中に生えた苔を退治したい時、ホームセンターで売っている強力な除草剤を使おうと考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、一般的な雑草用除草剤(非選択性と呼ばれるもの)は、苔だけでなく芝生も一緒に枯らしてしまう危険性が非常に高いです。せっかくの芝生が台無しになっては元も子もありませんよね。
芝生の苔対策には、必ず「芝生用」「選択制」と明記された苔専用の薬剤を選んでください。これらは芝生には影響を与えず、苔だけを枯らすように作られています。
また、「非農耕地用」と書かれた苔除去剤も、芝生には使えない場合が多いので注意が必要です。薬剤選びは慎重に行い、大切な芝生を守ってあげてください。
高圧洗浄機で素材(外壁・木材)を傷めない
高圧洗浄機は苔除去に非常に便利ですが、そのパワーゆえに扱いには注意が必要です。
特に外壁(サイディング)やウッドデッキなどの木材に使う場合、ノズルを近づけすぎたり、一点に集中して当て続けたりすると、素材の表面を傷めてしまう可能性があります。
塗装が剥がれたり、木材がささくれて毛羽立ったり、ひどい場合はサイディングの防水コートを傷つけたり、シーリング(目地)を破損させて雨漏りの原因になることもあります。
高圧洗浄機を使う際は、必ず対象物から適切な距離(15~30cm以上)を保ち、圧力を調整できる機種であれば一番弱い設定から試すようにしてください。自信がない場所や、劣化した素材の場合は、無理せずプロに任せるのが賢明です。
ペットや子供、他の植物への安全性(薬剤使用時)
苔除去剤や除草剤を使用する際は、ご家族やペット、周囲の植物への安全配慮が最も重要です。薬剤は、それが「自然由来」や「安全」を謳うものであっても、散布中や直後は注意が必要です。
小さなお子様やペット(犬、猫など)が、薬剤が乾く前に触れたり、舐めたりしないよう、散布当日は作業エリアに立ち入らせないように徹底してください。
作業は風のない日を選び、薬剤が大切な庭木や花壇、お隣の敷地に飛散しないよう十分注意しましょう。作業するご自身も、手袋、長袖、できれば保護メガネやマスクで防備してください。
散布後は、薬剤がしっかり乾燥・浸透するまで半日~1日ほど時間を置き、その後で軽く水を撒いて表面を流しておくと、ペットが舐めてしまうリスクを減らせるので安心ですね。
コケと雑草を除去して人工芝で再発を防止したY様邸の施工事例

記事の冒頭でご紹介した、奈良市のY様邸のケースを覚えておいででしょうか。「草は抜けるけど、苔だけはどうにもならない」と、ご自宅の裏庭を覆うしつこい苔に長年心を痛めておられました。
雨が降るたびにぬかるみ、お子様が外で遊ぶことも難しい状態だったそうです。
Y様のご要望は、「人工芝にして、子どもが安心して走り回れる庭をつくりたい」というものでした。私たち西原造園は、このお悩みを解決するため、見た目を綺麗にするだけでなく、苔の根本原因である「排水性」に着目した施工を行いました。
1. 根本原因の特定と「砕石の厚み・水勾配」による排水対策

Y様邸の裏庭は、日当たりが悪いことに加え、周りの家より土地が50cmほど低く、雨が降ると地下にできた水脈から水が流れ込む状態でした。これが、苔がこれほどまでに繁殖した根本原因の一つだったのです。
そこでまず、現在の土を鋤取(すきと)った後、下地として砂利(砕石)を厚めに敷き詰め、排水性を高める対策を行いました。

ただ人工芝を敷くだけでは、土台が湿ったままなので苔が再発する可能性があります。この砕石層が、地中の水分を素早く逃がす重要な役割を果たします。
さらに、Y様は自転車置場としても使いたいというご要望があったため、通路部分はRC砕石で地盤をより強固にしました。

2. 人工芝のための「下地づくり」(透水シート・真砂土整地)
砕石で排水層を作っただけでは、その上に入れた土が時間とともに砕石の隙間に沈んでしまい、地面が凸凹になってしまいます。そこで、砕石層の上に透水シート(水を通すシート)を敷設します。
これにより、土の流出を防ぎつつ、水だけを下に通すことができます。
その上に、人工芝の下地として最適な、水はけが良く整地しやすいきれいな土(真砂土)を入れていきます。

この真砂土を、コンパクター(転圧機)やタンパーといった専門の機械を使い、壁際までしっかりと締め固め、平らにしていきます。この下地づくりが、人工芝を美しく仕上げるための最も重要な工程の一つです。

3. 自転車通路の施工と防草・人工芝の「仕上げ」
自転車が通る通路は、さらに強度を持たせるため、真砂土にセメントを混ぜ込んで地盤を固めました。これで自転車の重みで轍(わだち)ができるのを防ぎます。

下地が完成したら、いよいよ仕上げです。まず、人工芝専用の防草シートを敷き詰めます。このシート選びを間違うと、人工芝が波打つようにシワになってしまうため、私たちは防草効果と美観を両立する専用品を使用しています。

シートの繋ぎ目は防水テープでしっかり塞ぎ、土が漏れ出すのを防ぎます。

最後に人工芝を敷設し、雨樋や汚水桝の蓋の形に合わせて、ミリ単位で慎重にカットしていきます。ピンで固定する際も、DIYでよくあるようにピンの頭が目立たないよう、どこにピンがあるか分からないレベルで仕上げるのがプロの仕事です。

こうして、苔とぬかるみに悩まされたお庭は、お子様が裸足で走り回れる、明るく広々とした空間へと生まれ変わりました。
Y様のお客様の声とビフォー・アフター
こうして無事に完成したY様邸のお庭がこちらです。
雑草と苔に覆われ、雨が降るたびに泥だらけになっていたお庭は、人工芝ですっきりと生まれ変わりました。これでもう、大変だった草抜きや泥はねの心配もしなくてよくなり、お庭全体が明るく広々とした印象になりました。
何より、庭に出るたびにため息をついていたというお話でしたが、これからは安心して気持ちよくお庭に出られますね。
ドロドロで遊べなかったこのスペースで、お子様が裸足で走り回るという、新しい楽しみも生まれました。
⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません
ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。
間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。
そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。
奈良県限定!
庭の苔除去に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、お客様からよくいただく庭の苔に関するご質問にお答えします。
地面のコケはどうやって除去すればいいですか?
地面(土)に生えた苔は、まずスコップや移植ゴテで表土ごと薄く削り取るのが手軽で確実です。苔とその下の土を数センチ程度取り除いてください。ただ、土壌の環境(湿気や酸性度)がそのままだと再発しやすいため、削り取った後に消石灰や苦土石灰を撒いて土のpHを中和したり、水はけを良くする川砂などを混ぜ込むといった土壌改良を行うと、より効果的です。広範囲で何度も再発する場合は、苔用の除草剤を散布する方法もありますが、根本的な排水対策(暗渠排水など)が必要かもしれません。
苔は取ったほうがいいですか?
結論から言うと、基本的には取ったほうが良いです。苔庭のように意図的に管理されている場合は別ですが、ご自宅のコンクリートや芝生などに意図せず生えてくる苔は、放置すると様々なデメリットがあります。最も危険なのは、雨などで濡れた際に非常に滑りやすくなり、転倒事故の原因になることです。また、家の美観を損ねて古びた印象を与えますし、芝生の中に広がると、芝生の光合成や養分の吸収を妨げ、生育を阻害する可能性もあります。
苔の除去に最適な時期・季節はいつですか?
苔除去の作業自体は、思い立ったらいつでも可能ですが、効率や再発防止の観点から言うと、秋(9~11月頃)や春先(3~4月頃)がおすすめです。梅雨時(6~7月)は苔が最も活発な時期なので、除去してもすぐに再発しやすいため不向きです。一方、秋は夏の間に繁殖した苔を取りやすく、除去後に土壌改良(石灰撒きなど)をして冬を迎えるのに適しています。春先は、冬の間に弱った苔を除去しやすく、これから成長する芝生や他の植物が苔の再発を抑えてくれる効果も期待できます。
庭の苔に重曹をまくとどうなる?
重曹(弱アルカリ性)を苔に撒くと、苔の細胞にダメージを与え、一応は枯らす効果があります。しかし、その効果は比較的穏やかで、市販の専用薬剤に比べると効果は低いとされています。また、庭土や芝生の上に大量に撒くと、土壌のpHが急激にアルカリ性に傾き、苔だけでなく芝生や他の植物まで枯らしてしまうリスクがあります。そのため、使用するとしてもコンクリートやベランダの薄い苔に限定し、土の上で使うのは避けたほうが賢明です。
土に苔が生える原因は何ですか?
土に苔が生える主な原因は、「湿気が多い」、「日陰」、「土壌が酸性」の3つの条件が揃っていることです。まず、苔は乾燥に弱いため、水はけが悪い粘土質の土壌や、常にジメジメしている場所でないと繁殖できません。次に、苔は強い直射日光を嫌うため、庭木や建物の陰になる日当たりの悪い場所を好みます。そして、多くの苔は弱酸性の土壌(pH5.0~6.0程度)を好むため、土が酸性に傾いていると、他の植物が育ちにくくなる一方で苔が優勢になってしまいます。