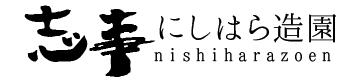「もう、この雑草との戦いを終わりにしたい…」 その長年の悩みに終止符を打つ、最も確実で永続的な解決策が、庭の雑草対策としてのコンクリートです。
土間コンクリートにすることで、毎年繰り返される草むしりの重労働から解放されることを想像すると、期待が膨らみますよね。
しかし、その効果が絶大であるからこそ、費用やデザイン、10年後のメンテナンスまで見据えた『正しい知識』がなければ、「こんなはずじゃなかった」という後悔に繋がってしまいます。
この記事は、あなたが10年後も「やってよかった」と心から満足できる雑草対策で最強ののコンクリート工事を実現するための羅針盤です。奈良で2000件以上のお庭づくりをお手伝いしてきたプロの全知識を、分かりやすく解説していきます。
この記事を読むと以下のことがわかります:
- コンクリートが雑草対策に「最強」と言われる本当の理由と、その限界
- 庭をコンクリートにする際の具体的なメリット・デメリット
- 業者依頼とDIY、それぞれのリアルな費用相場と安く抑えるコツ
- 土間コンクリートや透水性コンクリートなど、種類ごとの特徴と選び方
- プロが現場で見る、よくある失敗例とその回避策
- コンクリート以外の選択肢(砂利・人工芝など)との費用対効果の比較

西原 智(西原造園 代表)
奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人
奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。
職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。
これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。
本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。
全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。
そもそも庭の雑草対策にコンクリートは本当に有効?効果と限界

お庭や駐車場の雑草対策としてコンクリートを検討するとき、多くの方がその「永続性」に期待を寄せられます。
一度施工すれば、もうあの面倒な草むしりから解放されるのではないか、と。この章では、コンクリートが雑草対策としてなぜこれほど効果的なのか、その根本的な理由と、一方でプロとして知っておいていただきたい「限界」について、正直にお話しします。
コンクリートが「雑草対策で最強」と言われる3つの理由
「コンクリートにすれば本当に草が生えなくなるの?」その答えは、コンクリートが持つ3つの物理的な特性にあります。
まず第一に、光を完全に遮断する「遮光性」です。植物は光合成なしでは生きられません。防草シートでは突き抜けてくるような強い雑草も、分厚いコンクリートの前では成長を完全に止められます。
第二に、根を張る隙を与えない「物理的障壁」としての役割です。雑草はわずか数ミリの隙間でも根を伸ばそうとしますが、適切に施工されたコンクリートにはその隙間が存在しません。
そして第三に、水分や養分を保持しない「無機質な表面」です。表面に土埃が溜まらない限り、種子が飛来しても発芽するための環境が整わないのです。
この3つの原理が組み合わさることで、他のどの方法よりも確実で永続的な防草効果が期待できる、というわけです。
知っておくべき限界と注意点|防草コンクリートでも“永久”ではない
最強と言われるコンクリートですが、残念ながら「永久に完璧」というわけではありません。
多くの方が見落としがちなのが、コンクリートが持つ「伸縮」という性質です。コンクリートは固まる過程でわずかに収縮し、さらに季節の温度変化で膨張と収縮を繰り返します。
そのため、お住まいの基礎やブロック塀との境目には、どうしても数ミリ程度の隙間ができてしまうのです。
そして、このわずかな隙間こそが、スギナやチガヤ、しつこい芝生といった地下茎で増える雑草たちの格好の侵入口になります。彼らは光を求めて地下を横に伸び、こうした弱点を見つけては突き破って顔を出してくる。これがプロの現場でも最も注意を払う点の一つです。
もちろん、それとは別に、コンクリートの表面自体に溜まった土埃に種が飛来して根付くケースもあります。特に水はけの悪い場所では、表面に薄くコケが生え、それが土の代わりとなって小さな雑草の温床になることも。
「コンクリートを打ったから、もう何もしなくていい」というわけではないのです。定期的な掃除など、最低限のメンテナンスをすることで、その防草効果を長く維持できる、ということを覚えておいてくださいね。
次の章では、こうした特性を踏まえた上で、コンクリート化の具体的なメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
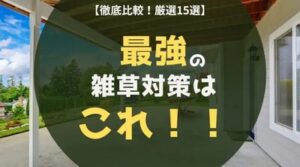
雑草対策でお庭を土間コンクリート化するメリット・デメリット

「お庭を土間コンクリートにすれば、長年の悩みだった雑草問題が解決する」。多くの方がそう期待されますよね。もちろん、その効果は絶大ですが、物事には必ず光と影があります。
良い面だけを見て決めてしまうと、数年後に「こんなはずじゃなかった」と後悔にも繋がりかねません。
ここでは、私が現場で見てきたコンクリート化の本当のメリットと、意外と知られていないデメリットの両方を、包み隠さずお話しします。
メリット1:雑草だけでなく「ぬかるみ・泥はね・害虫」も防ぐ
お客様から「雑草がなくなったのはもちろん嬉しいけど、実はそれ以上に…」と喜ばれるのが、この「ぬかるみ」と「泥はね」の問題解決です。
雨が降るたびに庭がぬかるんで歩きにくかったり、跳ねた泥で建物の基礎や窓が汚れたり…といった地味なストレス、ありませんか?コンクリートは地面を固めるので、こうした問題も一挙に解決します。
さらに、ジメジメした土壌はダンゴムシやナメクジといった害虫の温床になりがちですが、その発生源自体をなくす効果も期待できます。お庭全体が衛生的になる、というのも大きなメリットですね。
メリット2:水洗いで掃除が完結|庭が安全な多目的スペースに
土の庭や砂利敷きと大きく違うのが、掃除の圧倒的な手軽さです。
落ち葉や砂埃はホウキで掃くだけで済みますし、汚れが気になったらホースで水を流すだけ。年に一度、高圧洗浄機をかければ、新設時のような綺麗さが蘇ります。
そして、この「平らで硬い地面」は、暮らしの可能性を大きく広げてくれます。
これまで雑草に悩まされていた場所が、お子様のビニールプールや自転車の練習場所に、あるいはご友人を招いてのBBQスペース、DIYの作業台など、安全な多目的スペースへと生まれ変わるのです。
お庭の活用方法が劇的に変わった、というお声は本当に多いですね。
デメリット1:地下配管トラブル時の対応が困難
庭のコンクリート化を考える上で、多くの方が見落としがちなのが、地面の下に隠れた「見えないリスク」です。
どいう事かというと、お住まいの地中には、生活に不可欠な給水管・排水管・ガス管といった重要なライフラインが埋設されています。
普段、その存在を意識することはほとんどありませんが、万が一、これらの配管が老朽化などで破損・水漏れを起こした場合を想像してみてください。土の地面であれば、問題箇所を掘削して修理するだけで済みます。
しかし、庭がコンクリートで覆われている場合、その単純な修理の前に、まずコンクリート自体を破壊・撤去するという、別の工事が必須工程として加わります。
その結果、本来なら数万円で済むはずの配管修理が、コンクリートの撤去と再設置の費用を含めて数十万円規模の予期せぬ出費に膨れ上がるのです。
その結果、本来であれば配管の修理費用だけで済むはずが、そこにコンクリートを「壊す費用」と、綺麗に「やり直す費用」という、二つの大きな追加費用が発生してしまいます。
この「万が一の際の修理が、単純な作業ではなく大掛かりな工事になってしまうリスク」は、コンクリート化の長期的なデメリットとして、注意しておきたい点です。
デメリット2:夏場の照り返しが強く、熱がこもりやすい
コンクリートは、太陽の光と熱を吸収し、その熱を内部に溜め込みやすい性質を持っています。
その結果、夏場の強い日差しを受けると、表面温度は裸足で歩けないほどの高温、時には60℃近くにまで達します。これは、地面との距離が近い小さなお子様やペットにとっては、火傷につながる大変危険な状態です。
さらに問題なのが、蓄えた熱の放射と、太陽光の強い照り返しです。この反射熱がリビングなどの室内に侵入し、室温を上昇させ、エアコンの効きを悪くする原因にもなります。
「庭に出て涼む」という夏の楽しみ方が難しくなるだけでなく、住環境全体の快適性や光熱費にまで影響を及ぼす可能性がある。この点は、コンクリートがもたらす暮らしの影響として、注意しておきましょう。
デメリット3:一度施工すると撤去や変更が極めて困難
コンクリート化が他の雑草対策と決定的に違うのは、庭の一部が半永久的な「構造物」に変わってしまう点です。今は雑草対策が最優先でも、10年、20年と暮らす中でライフスタイルが変わる可能性は十分にあります。
例えば、「定年退職したので、小さな家庭菜園スペースを作りたい」と思っても、一度固めてしまったコンクリートをDIYで元に戻すことは、ほぼ不可能です。
砂利敷きであれば時間をかければご自身で撤去することもできますが、コンクリートは全く別次元の話になります。
撤去するには、専門業者が重機を使ってコンクリートを破壊し、運び出すという大掛かりな工事が必須となります。
将来の暮らしの変化に柔軟に対応することができなくなる、この「後戻りのできない」性質こそ、コンクリートを選ぶ上で注意しておきたい最大のポイントと言えるでしょう。
【費用を徹底比較】庭のコンクリート料金相場と安く抑えるコツ

メリット・デメリットを理解した上で、次はいよいよ最も現実的な「費用」の話に進みましょう。多くの方が「結局いくらかかるの?」と一番気にされる部分です。
業者に頼んだ場合のリアルな相場から、ご自身で挑戦するDIYの費用、そしてプロが実践するコストを抑えるコツまで、具体的にお話ししますので、ご自身の予算と照らし合わせながら読み進めてみてください。
業者に依頼する場合の費用相場
まず、我々のようなプロにご依頼いただく場合の費用ですが、よく目安としてお伝えするのが1平方メートルあたり10,000円~15,000円です。
ただ、「コンクリートを流すだけでそんなにかかるの?」と思われるかもしれませんが、実はこの金額には様々な工程が含まれています。
地面を掘削して平らにする「鋤取り・転圧」、コンクリートが流れ出ないようにする「型枠設置」、強度を保つための「ワイヤーメッシュ敷設」、そして最後に表面を綺麗に仕上げる「左官仕上げ」まで。これら全てを含んだ価格なんです。
例えば、以下の要素によって費用が変動します。
- 庭の状態(傾斜の有無・整地の必要性)
- コンクリートの種類(土間コンクリート、透水性コンクリートなど)
- 厚み(厚さ10cm以上なら強度が増すが、費用もアップ)
- 仕上げ方法(刷毛引き仕上げ、金ゴテ仕上げなどの違い)
- 業者による違い(地域や施工会社の価格設定)
もちろん、重機が入れない狭い場所や、既存のものを撤去する必要がある場合は追加費用がかかることもありますね。なので、冒頭の単価は、あくまで基本的な条件での目安と考えてください。
では、この単価を元に、次で具体的な面積で総額がいくらになるのか計算してみましょう。
【面積別】10㎡・30㎡・50㎡の費用シミュレーション
先ほどの単価を使っても、なかなか総額がイメージしにくいですよね。ここでは代表的な面積でシミュレーションしてみましょう。
| 庭の広さ | 費用相場(業者依頼) |
|---|---|
| 5㎡(約畳3枚分) | 40,000円~75,000円 |
| 10㎡(約6畳) | 10,000円~150,000円 |
| 20㎡(駐車場1台分) | 160,000円~300,000円 |
| 30㎡(広めの庭) | 300,000円~450,000円 |
| 50㎡(広めの庭) | 500,000円~750,000円 |
例えば10㎡、これは軽自動車1台分の駐車スペースくらいの広さですが、費用は約10万円~15万円が目安です。
一般的なお庭でよくご依頼いただく30㎡(約9坪)ですと約30万円~45万円。
そして、かなり広めの50㎡になると約50万円~75万円ほどになります。
ご自宅のお庭のおおよその面積と照らし合わせると、具体的な予算感が見えてくるのではないでしょうか。
この金額を見て、「やっぱり高いな…DIYならどうだろう?」と考える方もいらっしゃいますよね。では次に、DIYの場合の費用を見ていきましょう。
DIYで施工する場合の費用目安と材料内訳
ご自身で挑戦するDIYの場合、費用は業者に頼むよりも格段に安く抑えられます。
かかるのは主に材料費と道具代ですね。10cmの厚さでコンクリートを打つと仮定すると、セメント・砂・砂利・ワイヤーメッシュといった材料費は、1㎡あたり3,000円~5,000円程度に収まることが多いです。
DIYの費用内訳(10㎡の場合)
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| コンクリート(生コン) | 30,000円~ |
| 砕石・砂 | 5,000円~10,000円 |
| 型枠(木材) | 5,000円~8,000円 |
| ワイヤーメッシュ(鉄筋) | 3,000円~6,000円 |
| 道具代(コテ・スコップ・バケツなど) | 5,000円~15,000円 |
| 合計 | 33,000円~69,000円 |
ただし、DIYの場合は材料を揃えるだけでなく、整地作業やコンクリートを流し込む作業が必要なため、体力と時間がかかる点も考慮しましょう。
費用の内訳(業者依頼の場合)
業者に頼むと、材料費以外にも施工費や諸経費がかかります。具体的な費用内訳を見てみましょう。
| 費用項目 | 具体的な内容 | 費用目安(10㎡の場合) |
|---|---|---|
| 材料費 | コンクリート、砕石、型枠、ワイヤーメッシュ | 30,000円~50,000円 |
| 工事費 | 掘削・整地、型枠設置、コンクリート打設、仕上げ、養生 | 50,000円~80,000円 |
| 諸経費 | 人件費、運搬費、廃棄物処理費 | 10,000円~20,000円 |
| 合計 | 90,000円~150,000円 |
このように、業者に依頼すると人件費や諸経費がプラスされるため、DIYより費用は高くなります。しかし、施工のクオリティが保証されるため、「長持ちさせたい・仕上がりをキレイにしたい」場合はプロに頼むのが安心です。
DIYと業者で比較|施工費用(10㎡の場合)の比較表
| 施工方法 | 費用相場(10㎡) | 施工時間 | 仕上がりの品質 | メンテナンス | 労力 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者依頼 | 90,000円~150,000円 | 1~2日 | ◎(プロの仕上がり) | 〇(長持ちしやすい) | 少ない | あり(業者による) |
| DIY | 33,000円~69,000円 | 数日~1週間 | △(仕上がりにばらつき) | △(施工ミスがあると補修が必要) | 多い | なし |
見積もり前に知りたい!費用を安く抑える3つのコツ
「庭をコンクリートにしたいけど、できるだけ安く済ませたい…」と考えている方も多いのではないでしょうか?コンクリート施工は、業者に依頼すると高額になりがちですが、工夫次第で費用を大幅に抑えることが可能です。
ここでは、「庭 コンクリート 安い」を実現するための3つの秘訣を紹介します。コストを抑えながら、満足のいく仕上がりを目指しましょう!
秘訣1:DIYに挑戦する
コンクリート施工の費用が高くなる理由のひとつは「人件費」です。業者に依頼すると材料費に加えて作業費が発生するため、自分で施工すればその分のコストを削減できます。特に、小さな庭や駐車場の一部をコンクリートにする場合は、DIYでの施工が費用対効果の高い選択肢となります。
DIYでは、生コンや型枠を自分で準備し、コンクリートを流し込む作業を行います。スコップやコテ、ワイヤーメッシュなどの道具を揃える必要がありますが、一度道具を購入すれば、今後の補修や別の施工にも活用できます。ただし、施工には時間と労力がかかり、均一に仕上げるのが難しいため、作業計画をしっかり立てることが重要です。
✅ DIYのポイント
- 人件費を削減できるため、業者依頼の半額以下で施工可能
- 道具や材料の準備が必要だが、今後も使えるため無駄にならない
- 施工の手順をしっかり学び、計画的に作業を進める
秘訣2:材料費を抑える(DIYの場合)
DIYで行う場合、材料費を抑えることでコストダウンが可能です。というのは、コンクリート施工の費用の中でも、大きな割合を占めるのが「材料費」です。DIYで行う場合は生コンや砕石、型枠などのコストを抑えることで、全体の予算を下げることができます。
材料費を節約する方法はいくつかあります。まず、ホームセンターを活用すると、業者を通さずに材料を直接購入できるため、無駄な中間マージンをカットできます。
また、ネット通販ではまとめ買いやセールを利用すると安く手に入ることがあり、特に重たい生コンは配達してもらうことで手間を減らせます。さらに、型枠や工具は中古品を探すことで大幅に節約でき、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを活用するのもおすすめです。
ただし、安すぎる材料を選ぶと品質が悪く、ひび割れや劣化の原因になることもあるため、価格と品質のバランスを見極めることが重要です。
✅ 材料費を抑える方法
- ホームセンターやネット通販を活用して直接購入
- まとめ買いやセールを利用してコストダウン
- 型枠や工具は中古品を活用し、購入費を抑える
- 安すぎる材料には注意し、品質とのバランスを考える
秘訣3:業者選びを工夫する
「DIYは難しそう…でも業者に頼むと高額になりそう…」と悩んでいる方も多いでしょう。コストを抑えながらも満足のいく仕上がりにするためには、信頼できる業者を選ぶことが何より大切です。ただ安さだけを追求するのではなく、相談に乗ってくれる業者を探し、自分の庭に合った方法を提案してもらうことで、費用を抑えつつ理想の庭づくりができます。
■相談に乗ってくれる業者を探す
コンクリート施工を依頼する際、こちらの希望や予算をきちんと聞き、相談に乗ってくれる業者を選ぶことが重要です。「予算は〇〇円以内で抑えたい」「予算内で理想を実現する方法はあるか?」「代替案があるか?」といった質問に親身に対応してくれるかどうかを確認しましょう。打ち合わせの段階で、とにかく無理に価格を安くする業者や、説明が不明瞭な業者は避けたほうが無難です。
■ハウスメーカーより外構・造園業者を探す
コンクリートの施工は、ハウスメーカーよりも外構・造園業者に依頼するほうが費用を抑えやすい傾向にあります。工務店は住宅全般を扱うため、外構工事の専門知識が浅いこともあり、中間マージンが発生することが多いからです。一方、外構や庭の施工を専門にしている業者なら、効率よく工事ができるため、比較的安価に施工してもらえる可能性があります。
■地域密着の業者を選ぶ
全国展開の大手業者よりも、地域密着型の外構・造園業者に依頼するほうがコストを抑えやすいことがあります。地域の業者は移動費や運搬費がかかりにくく、その分のコストを削減できるからです。また、地元の評判を重視しているため、アフターケアや相談にも柔軟に対応してくれることが多いのもメリットのひとつです。
✅ 業者選びのコツ
- 地域密着の業者を選ぶと、コストを抑えながら質の高い施工が受けられる
- こちらの要望を丁寧に聞き、相談に乗ってくれる業者を選ぶ
- 工務店よりも外構・造園業者を優先して探す
業者に頼む?DIYでできる?費用と仕上がりで見る判断基準
費用の相場観が見えてくると、次に悩むのが「これを自分でやるべきか、プロに任せるべきか」という点ですよね。特に一戸建てのお庭や玄関アプローチなど、家の顔となる場所では、仕上がりの質も気になるところ。
この章では、費用、品質、手間の観点から、どちらがあなたにとって最適な選択なのか、その判断基準を具体的に解説します。
| 項目 | DIY施工 | 業者依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 約 33,000円~69,000円(10㎡) | 約 90,000円~150,000円(10㎡) |
| 施工時間 | 数日~1週間以上(作業ペースによる) | 1~2日で完了 |
| 仕上がりの品質 | △(ムラが出やすく、ひび割れのリスクあり) | ◎(プロの技術で美しい仕上がり) |
| メンテナンス | △(施工ミスがあると追加補修が必要) | 〇(耐久性が高く、保証付きの場合も) |
| 労力・負担 | 大きい(整地・型枠設置・コンクリート流し込みなどの重労働) | ほぼなし(業者に任せるだけ) |
| 必要なスキル | あり(均一な施工やひび割れ対策が必要) | 不要(プロがすべて対応) |
| 道具・材料の準備 | 必要(コンクリート、砕石、型枠、ワイヤーメッシュなど) | 不要(すべて業者が用意) |
| 保証の有無 | なし(トラブル時は自己負担で修正) | あり(業者による保証あり) |
| 適している人 | 「費用を抑えたい」「DIYが好き」「時間に余裕がある」 | 「仕上がりを重視したい」「早く完成させたい」「DIYに自信がない」 |
| 向いていない人 | 「体力がない」「ムラのない仕上がりを求める」「短期間で仕上げたい」 | 「コストを抑えたい」「DIYを楽しみたい」 |
業者依頼のメリット・デメリット
私たちプロにご依頼いただく最大のメリットは、やはり仕上がりの美しさと耐久性です。コンクリート工事は、ただ流し込むだけではありません。
その下の地面を固める「転圧」や、雨水がたまらないように計算された「水勾配」、そして表面を滑らかに仕上げる「左官技術」など、目に見えない部分にこそプロの技が詰まっています。これらがしっかりしていないと、数年でひび割れや水たまりといったトラブルに繋がります。
また、万が一の不具合に対応する「保証」があるのも大きな安心材料ですよね。デメリットは、やはりDIYに比べて費用が高くなる点です。
しかし、10年、20年先まで続く安心と美しさを手に入れるための「投資」と考えれば、その価値は十分にあると私は思います。
では次に、DIYのメリットとデメリットについても見ていきましょう。
DIYのメリット・デメリット
DIYの最大の魅力は、なんといっても費用の安さです。人件費がかからないため、材料費だけで済ませられれば、業者に依頼する半額以下で収まることもあります。
自分の手で庭を綺麗にしていく達成感や、自分の好きなようにデザインできる自由度の高さも、DIYならではの楽しみですよね。
しかし、その裏には相応の覚悟が必要です。まず、想像を絶するほどの重労働であること。セメントや砂利を運び、練り上げる作業は、体力に自信のある男性でも音を上げるほどです。
また、コンクリートは一度練り始めたら待ってくれません。段取りの悪さが、そのまま仕上がりの失敗に直結します。「安く済ませようとしたのに、結局失敗して業者に高くついた」というご相談は、実は非常に多いのです。
この違いを踏まえて、それぞれどんな人に向いているのかを考えてみましょう。
こんな人は業者依頼がおすすめ
もし、あなたがこれから挙げる項目のいずれかに当てはまるなら、迷わずプロへの依頼を検討することをおすすめします。
まず、10㎡を超えるような、ある程度の広さを施工したい場合。個人で扱うには材料の量も労力も膨大になります。次に、駐車場など車の重量がかかる場所への施工。これは基礎の作り方が非常に重要で、強度不足は大きな事故に繋がりかねません。
そして何より、仕上がりの見た目に絶対に妥協したくない方や、週末の貴重な時間を重労働ではなくご家族と過ごしたい方。
美観と安心、そして時間を買うという意味で、プロに任せる価値は十分にあります。「餅は餅屋」という言葉がありますが、コンクリート工事はまさにその典型だと、私は長年の経験から感じています。
では、DIYに向いているのはどんな人なのでしょうか。
こんな人はDIYに挑戦できる
一方で、DIYに挑戦できるのはどんな人でしょうか。まず大前提として、施工面積が物置の下や勝手口の足場など、ごく小規模(2~3㎡程度)であることです。このくらいの広さであれば、砂とセメントで対応できる範囲です。
また、過去にブロック積みなどのDIY経験があり、体力にも自信がある方。そして何より、「失敗も経験の一つ」と楽しめる探究心のある方です。
完璧な仕上がりを求めるのではなく、多少の歪みや色ムラも「味」として愛せるのであれば、挑戦する価値はあるでしょう。ただし、必ず事前に施工方法をしっかり調べ、無理のない計画を立てることが成功の秘訣です。
さて、どちらの方法を選ぶにしても、次に重要になるのが「どのコンクリートを使うか」です。次の章では、その種類と選び方について詳しく解説します。
ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。
ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。
実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。
自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。
ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。
あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇
参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >
どのコンクリートを選ぶ?特徴と違い【主要4種類を比較】
さて、業者に頼むか、DIYで挑戦するかの方向性が見えてきたら、次は「どの種類のコンクリートを使うか」という具体的な選択肢について考えていきましょう。
「コンクリート」と一括りにされがちですが、実はいくつかの種類があり、それぞれに特徴、見た目、そして費用が異なります。
お庭の場所や目的、そしてデザインのお好みに合わせて最適なものを選ぶことが、後悔しないための重要なポイントになります。
土間コンクリートの特徴

まずご紹介するのが、最も一般的で、皆さんが「コンクリート」と聞いてイメージするであろう「土間(どま)コンクリート」です。
これは、我々プロが駐車場やお庭の広い面積を施工する際に標準的に使用するもので、いわばコンクリート界の王道ですね。
現場でセメント、砂、砂利、そして水を練り混ぜて作り、強度を出すために中にワイヤーメッシュ(鉄筋)を敷設するのが一般的です。
その最大の特徴は、コストと強度のバランスに優れていること。車が乗るような場所にも十分耐えられる高い耐久性を持ちながら、後述する特殊なコンクリートに比べて費用を抑えることができます。
表面はコテで平滑に仕上げるため、掃除がしやすく、見た目もスッキリとします。特別なこだわりがなければ、まずこの土間コンクリートを基準に考えていただくのが良いでしょう。
土間コンクリートのメリット
- 強度・耐久性が高い
土間コンクリートは、駐車場や車の乗り入れがある場所に最適なほど強度が高く、重いものが載っても割れにくいです。 - 雑草抑制効果が高い
コンクリートで地面を完全に覆うため、雑草が生える余地がなく、除草の手間が大幅に減るのが大きなメリットです。 - メンテナンスが容易
基本的に水洗いだけで掃除が可能なので、手入れの負担が少なく済みます。 - 費用相場が比較的安価
透水性コンクリートやデザイン性の高いコンクリートよりも施工費が抑えられるため、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。
土間コンクリートのデメリット
- 透水性がない
水を通さないため、排水対策をしないと水たまりができやすいという欠点があります。 - ひび割れしやすい
経年劣化によるひび割れが発生することがあり、特に寒冷地では凍害による損傷も考慮する必要があります。 - 夏場の照り返しが強い
日光を吸収しやすいため、表面温度が高くなり、庭が暑くなりやすいというデメリットがあります。 - デザインのバリエーションが少ない
一般的なコンクリートは無機質な印象を与え、ナチュラルな雰囲気の庭には馴染みにくいことがあります。
土間コンクリートの費用相場(業者依頼 vs DIY)
| 施工方法 | 費用相場(1㎡あたり) | 総費用(10㎡) |
|---|---|---|
| 業者依頼 | 8,000円~15,000円 | 80,000円~150,000円 |
| DIY | 4,000円~7,000円 | 40,000円~70,000円 |
業者に依頼すると、品質の高い仕上がりが保証されますが、費用が高くなる傾向があります。一方、DIYならコストを抑えられますが、施工の手間と仕上がりの均一性には注意が必要です。
どんな庭におすすめ?
✅ 駐車場や車の乗り入れがある場所
✅ 玄関アプローチや駐輪スペース
✅ シンプルでメンテナンスが楽な庭を求める人
透水性コンクリートの特徴・メリット・デメリット
最近、特にお問い合わせが増えているのが、この「透水性コンクリート」です。その名の通り、内部に無数の隙間があり、雨水を地面へと浸透させる機能を持っています。
土間コンクリートとの一番の違いは、この「水はけの良さ」ですね。
メリットは、雨の日でも水たまりができにくいこと。これにより、お庭の衛生環境が保たれ、靴の汚れなども気にせずに済みます。
また、水を浸透させることで地下水への還元に繋がったり、打ち水効果で夏場の表面温度の上昇を和らげたりする効果も期待できます。
デメリットとしては、一般的な土間コンクリートに比べて材料費や施工費がやや割高になる点と、表面強度が少し劣るため、大型トラックなどが頻繁に通る場所には向かない場合があります。
透水性コンクリートのメリット
- 透水性が高い
雨水を地面に直接浸透させるため、水はけが良く、水たまりができにくいのが最大の利点です。 - 保水性があり、夏場の温度上昇を抑えられる
水分を保持するため、通常の土間コンクリートよりも表面温度が上がりにくいという特性があります。 - 雑草抑制効果が高い
地面を覆うため、土間コンクリートと同様に雑草が生えにくいというメリットがあります。
透水性コンクリートのデメリット
- 土間コンクリートより費用が高い
透水性のある特殊なコンクリートを使用するため、施工コストが高くなる傾向があります。 - 耐久性がやや劣る
土間コンクリートと比較すると、強度がやや低いため、重い車両を頻繁に乗せる場所には向かない場合があります。 - 長期的な実績が少ない
比較的新しい技術のため、耐久性や経年劣化に関するデータが少ないのが懸念点です。 - デザインのバリエーションが少ない
土間コンクリートに比べてカラーバリエーションや模様の選択肢が少ない。 - コンクリートのプラント(工場)が避ける傾向にある
透水性コンクリートは一般的な土間コンクリートと比べて練り混ぜる際の管理が難しく、強度や品質のばらつきが出やすいため、多くのコンクリートプラント(製造工場)で取り扱いを敬遠される傾向があります。そのため、入手できる地域が限られ、施工コストの増加につながる場合があります。 - 施工できる業者が少ない
時期や施工方法によって上手く固まらずに砂利の状態になる事もあるため、リスクが高く施工できる全国的に見ても業者が少ないです。※弊社では代替案があるので透水性コンクリートは取り扱っておりません。
透水性コンクリートの費用相場(業者依頼 vs DIY)
| 施工方法 | 費用相場(1㎡あたり) | 総費用(10㎡) |
|---|---|---|
| 業者依頼 | 10,000円~18,000円 | 100,000円~180,000円 |
| DIY | 5,000円~9,000円 | 50,000円~90,000円 |
どんな庭におすすめ?
✅ 雑草対策を最優先したい庭
✅ 水はけが悪く、雨の日の水たまりに悩んでいる庭
✅ DIYで庭を変えたいDIYer向け
✅ 環境に配慮した素材を選びたいユーザー
洗い出し仕上げの特徴・メリット・デメリット

「コンクリートの、あの灰色でのっぺりした感じがどうも苦手で…」そんなデザイン性を重視される方に、私がよくご提案するのが「洗い出し仕上げ」です。これはコンクリートの種類というより、表面の仕上げ方の技術ですね。
コンクリートが完全に固まる前に、表面のセメント部分を水で洗い流し、中に混ぜ込んである砂利(骨材)をわざと浮き立たせて見せる工法です。
メリットは、なんといってもその上品で自然な風合いです。
砂利の種類や色を変えることで、和風にも洋風にも合わせられる高いデザイン性を持ち、玄関アプローチなどに施工すると、お住まいの印象がぐっと引き立ちます。
また、表面がザラザラしているので滑りにくいという実用的な利点もあります。デメリットは、職人の高い技術が必要とされるため、通常の土間コンクリートに比べて施工費が高くなる点です。
洗い出し仕上げのメリット
コンクリートに混ぜ込む砂利の種類・色・大きさによって、多彩な表情を演出できるのが最大の魅力です。
和風庭園のしっとりとした雰囲気から、洋風のモダンなデザインまで幅広く対応でき、ありきたりなコンクリートにはない高級感と温かみをお庭に与えます。
洗い出し仕上げのデメリット
- 費用が割高になる
コンクリートが固まる最適なタイミングで表面を洗い流すなど、職人の高い技術と手間が必要となるため、一般的な土間コンクリートに比べて施工費用は高くなります。 - 施工に高い技術が必要(DIYは困難)
美しい仕上がりは、職人の経験と勘に大きく左右されます。洗い流すタイミングが早すぎても遅すぎても失敗するため、DIYで挑戦するには難易度が非常に高く、基本的にはプロに任せるべき工法です。 - 経年で黒ずみが目立ちやすい
表面の凹凸に長年かけて雨水やホコリが蓄積し、特に日当たりの悪い場所では黒ずみやコケが付着して、せっかくの風合いが損なわれることがあります。美しい状態を保つには、定期的な洗浄メンテナンスが欠かせません。
洗い出し仕上げの費用相場(業者依頼 vs DIY)
| 施工方法 | 費用相場(1㎡あたり) | 総費用(10㎡) |
| 業者依頼 | 12,000円~20,000円 | 120,000円~200,000円 |
| DIY | 6,000円~10,000円 | 60,000円~100,000円 |
職人の技術料が価格に反映されるため、土間コンクリートより高価になります。DIYは費用を抑えられますが、施工の難易度が極めて高く失敗のリスクも大きいため、プロへの依頼を強く推奨します。
どんな庭におすすめ?
✅ 玄関アプローチなど、家の顔となる場所
✅ 階段やスロープなど、滑りやすさを解消したい場所
✅ 和風・和モダン庭園の通路
✅ 無機質なコンクリートの見た目が苦手で、デザイン性を重視する人
【DIY】インスタントコンクリート(モルタル・セメント)の特徴・費用

最後に、DIYを検討されている方向けの選択肢です。ホームセンターに行くと、袋に入った「インスタントコンクリート」や「インスタントモルタル」が売られていますよね。
これらは、あらかじめセメントや砂が配合されており、水を加えるだけで使える手軽さが最大のメリットです。
物干し台の基礎や、フェンスの柱を一本だけ立てる、といったごく小規模な作業には非常に便利です。
費用も一袋(20kg)で1,000円前後からと手頃です。ただし、注意していただきたいのは、これはあくまで部分的な補修や小さなDIY向けだということ。
駐車場のような広い面積をこれで施工しようとすると、材料を一つずつ買うより逆に割高になり、大量の袋を運んで練る手間も膨大になります。プロの視点から見ると、DIYでの使用は2~3㎡程度が限界だと考えておいた方が良いでしょう。
セメント(モルタル)とは?特徴と基本情報
セメントは、DIYでも手軽に扱える建築材料のひとつであり、水と混ぜるだけで簡単に使用できます。ホームセンターなどで購入できるため、少量から施工が可能なのが特徴です。
また、セメントに砂を混ぜた「モルタル」も、DIYでよく使用される材料です。コンクリートよりも強度は低いものの、小規模な施工や補修には最適な素材です。
DIY初心者でも安心な理由
セメントは、専門的な技術や特殊な道具を必要とせず、初心者でも扱いやすいため、DIYに挑戦したい方におすすめです。
また、少量から購入できるため、「とりあえず試してみたい」という人でも気軽に導入できます。
セメントのメリット
- 費用が安い
他のコンクリート材料と比較すると、最も安価で手に入るため、費用を抑えたい方に最適。 - DIY初心者でも扱いやすい
施工がシンプルで、初心者でも簡単に作業できる。 - 少量から購入可能
必要な分だけ購入できるため、狭い範囲の施工や補修に向いている。 - ひび割れ補修や隙間埋めにも便利
コンクリートの補修や、小規模な施工に使いやすい。
セメントのデメリット
- 強度・耐久性が劣る
コンクリートに比べると強度が低く、駐車場など重量がかかる場所には適さない。 - 雑草抑制効果は限定的
透水性がないため、表面にコケや藻が生えやすく、長期間の雑草対策には不向き。 - 透水性がない
水を通さないため、水たまりができる可能性がある。 - 広い面積の施工には不向き
セメントは広範囲に施工するとひび割れしやすいため、大規模な施工には向いていない。
セメントの費用相場(DIY)
| 材料 | 費用相場(1㎡あたり) |
|---|---|
| セメント | 500円~1,000円 |
| 砂・混合材 | 500円~1,500円 |
| 合計 | 1,000円~2,500円 |
セメントはDIY施工が基本であり、材料費が非常に安価なのが最大のメリットです。
どんな庭におすすめ?
✅ 狭い範囲の施工(犬走り・花壇周りなど)
✅ コンクリートの隙間やひび割れ補修
✅ DIY初心者が手軽に試せる施工を探している
✅ 費用を最小限に抑えたいユーザー
| 項目 | 土間コンクリート | 透水性コンクリート | 洗い出し | セメント |
|---|---|---|---|---|
| 費用(㎡単価) | 8,000円~15,000円 | 10,000円~18,000円 | 15,000円~20,000円 | 1,000円~2,500円 |
| 耐久性 | ◎(約20~30年持続) | 〇(約15~25年持続) | 〇(約15~25年持続) | △(約5~10年持続) |
| 透水性 | ✖(透水性なし) | ◎(水はけが良い) | ✖(透水性なし) | ✖(透水性なし) |
| 雑草対策効果 | ◎(雑草完全防止) | ◎(雑草防止効果高い) | ◎(雑草完全防止) | △(部分的な防草向き) |
| DIY難易度 | △(業者推奨) | 〇(DIY可能) | ✖(DIY非推奨) | ◎(初心者向け) |
| デザイン性 | △(シンプル) | ✖(おしゃれとは言えない) | 〇(圧倒的におしゃれ) | △(シンプル) |
| メンテナンス性 | 〇(高圧洗浄) | △(目詰まりする) | 〇(高圧洗浄) | △(劣化しやすい) |
| おすすめの用途 | 駐車場、駐輪場、アプローチ、通路など | 水はけが悪い庭、排水先がない庭、雑草対策 | アプローチ、駐輪場、玄関前等 | 狭い範囲のDIY、小規模補修 |
コンクリートでおしゃれに雑草対策!デザイン事例集
私たちが手掛けるコンクリート工事は、単に雑草をなくす作業だけではなく、客様が抱える日々のストレスを解消し、お庭での暮らしそのものを豊かに変えるための「問題解決」に役立ちます。
ここでは、私が奈良県内でお客様のリアルな悩みに向き合い、コンクリート化によってその暮らしを改善した、3つの代表的な事例をご紹介します。
コンクリートで駐車場のぬかるみを改善して、水はけを良くした事例

この事例では、雨が降るとぬかるんで使えなかった土の駐車場をコンクリートで舗装し、水はけを大幅に改善しました。施工前は粘土質で水が捌けず、歩くと靴が泥だらけになり、車も停められない状態でした。
この問題を解決するため、地面に勾配をつけて水を一定方向に流す「表面排水」という手法を採用しました。具体的には、駐車スペースの道路側を全てコンクリートで舗装し、雨水が自然に道路側へ流れるように設計されています。
この工事により、水たまりやぬかるみが解消され、雨の日でも快適に車を停めたり歩いたりできるようになり、道路との段差もなくなりました。

コンクリートで雑草対策をした事例

この事例におけるコンクリート工事は、庭の雑草とぬかるみの問題を解決するために部分的に実施されました。主な目的は、管理が難しく、雨天時にぬかるんでしまう箇所のメンテナンス性を向上させることでした。
特に、勝手口の前は土のままだと雨の日に足元が汚れてしまうため、コンクリートを打設しました。これにより、雨が降った翌日でもぬかるむことなく、快適に出入りが可能になりました。
また、人が入りにくく草引きが大変な狭く危険な場所にもコンクリートを敷き詰め、草引きの手間を省きメンテナンスフリーにしました。

水はけが悪いお庭を、コンクリートにして改善する工事した事例

この事例では、水はけの悪い庭を全面的にコンクリートで舗装し、複数の問題を一挙に解決しています。施工前は、庭が土の状態で水はけが悪く、大雨の際には床下浸水の懸念もありました。
対策として、庭全体にコンクリートを打ち、雨水が表面を流れるようにしました。水が溜まらないよう、排水口の「会所」に向かって適切に傾斜をつけ、距離がある場所にはU字溝を設置して効率的に排水できる設計になっています。
また、アプローチはコンクリートスロープにし、表面を刷毛で仕上げる「刷毛引き」という工法で滑り止め効果を持たせました。この工事により、水はけが改善されただけでなく、自転車の出し入れもスムーズになりました。

庭のコンクリートの工事で後悔しないための注意点とよくある失敗例
デザインの素敵な事例を見て、夢が膨らんだ方も多いと思います。しかし、その美しい仕上がりは、確かな施工技術があってこそ。
残念ながら、知識不足や手抜き工事で「こんなはずじゃなかった」と後悔されているお庭も、私は数多く見てきました。ここでは、プロの現場でよく目にする代表的な失敗例と、それを未然に防ぐための本質的な注意点について、具体的に解説していきます。
失敗例1:水勾配不良で水たまりが発生

「雨が降った後、いつまでもお庭の隅に水たまりが残っている…」。これは、コンクリート工事の失敗例として、おそらく最も多くご相談をいただくケースです。
原因は「水勾配(みずこうばい)」の設計ミス。コンクリートの表面は、完全に水平に作るのではなく、雨水が自然に排水溝や道路側溝へ流れていくように、1.5~2%程度のわずかな傾斜をつけて施工するのが鉄則です。
この計算を怠ったり、施工が雑だったりすると、低い部分に水が溜まってしまいます。
水たまりは見た目が悪いだけでなく、コケやカビの発生源となり、表面がヌルヌルして滑りやすくなるなど、衛生面・安全面でも問題です。
一度固まってしまったコンクリートの勾配を後から修正するのは、ほぼ不可能です。最初の設計段階で、敷地全体の水の流れをどうデザインするかが、プロの腕の見せ所なのです。
失敗例2:ひび割れ(クラック)から雑草が再発
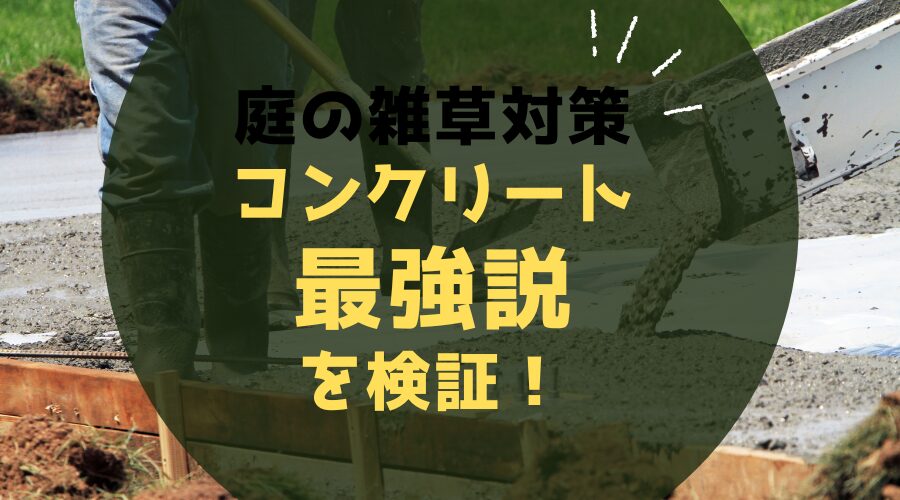
せっかく雑草対策のためにコンクリートにしたのに、ひび割れ(クラック)からまた雑草が生えてきた…これほどがっかりすることはありませんよね。
コンクリートの性質上、温度変化などで表面に細かな「ヘアークラック」が入ることは避けられませんが、問題なのはもっと大きな構造的なひび割れです。
この主な原因は、コンクリートを流す前の「下地作り」の手抜きにあります。
地面の転圧(突き固める作業)が不十分で地盤が均一でなかったり、クラッシャーランを敷いていなかったり、強度を確保するためのワイヤーメッシュ(鉄筋)を省いていたりすると、コンクリートが自重や車の重みに耐えきれず、大きなひび割れに繋がります。
多くの場合は、そもそも厚みが足りないことで割れてクラックが入る事が多いです。ある場所の雑草対策としてコンクリートを使う場合は最低でも7cmはコンクリートの厚みを取ることが賢明です。
万が一クラックが入ると、その割れ目に土が溜まり、結果として雑草の温床になってしまうのです。目に見えない下地作りをいかに丁寧に行うかが、コンクリートの寿命を決めると言っても過言ではありません。
失敗例3:無機質で“おしゃれな庭”から遠ざかる

これは技術的な失敗ではありませんが、「景観・デザイン面での後悔」も非常に多いご相談の一つです。
「雑草さえなくなればいい」と、ただ灰色のコンクリートを流し込んだだけでは、お庭はまるで倉庫の床のようになってしまいます。
温かみがなく、無機質で殺風景な空間になってしまい、リビングのカーテンを開けるのが憂鬱になった、というお声も耳にします。
これを防ぐには、事前の「デザイン計画」が不可欠です。
前の章でご紹介したように、スリットを入れて砂利や緑を加えたり、刷毛引き仕上げにしたり、洗い出し仕上げで表情をつけたりと、工夫次第でコンクリートの印象は大きく変わります。
またコンクリートはそれだけだと非常に無機質ですが、周囲に植栽を配置したり、ブロック塀のデザインやアプローチのデザイン、家の外観などでスタイリッシュでオシャレに見せる事もできます。
なので、コンクリート単体で考えるよりも、周囲の物をおしゃれにすることでコンクリートの無機質さを回避する事ができます。
「機能性」と「デザイン性」のバランスをどう取るか。ご家族がそのお庭でどう過ごしたいかをイメージしながら計画することが、満足度を高める鍵となります。
失敗例4:厚み不足による強度不足と破損

そして、最も深刻で危険なのが、この「厚み不足」による強度不足です。特に駐車場として使用する場合、コンクリートの厚みは非常に重要になります。
我々プロの世界では、車が乗る場所であれば厚さ10cm(ワイヤーメッシュ入り)が絶対的な基準です。
しかし、DIYで費用を抑えようとしたり、知識の浅い業者が材料をケチったりして、この基準に満たない厚みで施工してしまうケースが見られます。
厚みが足りないと、車の重みでコンクリートが耐えきれずにバキバキに割れたり、陥没したりする危険性があります。こうなってしまうと、補修は不可能です。
一度すべてを破壊して撤去し、ゼロからやり直すしかなく、結果的に最初の何倍もの費用がかかってしまいます。
さて、ここまでコンクリートの失敗例を見てきましたが、そもそもコンクリートだけが唯一の選択肢なのでしょうか。次の章では、他の雑草対策と比較して、それぞれの長所と短所を見ていきましょう。
コンクリートと他の雑草対策の比較
さて、ここまでコンクリートの様々な側面を深掘りしてきましたが、「本当に我が家にとってコンクリートがベストな選択なんだろうか?」と、他の選択肢も気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雑草対策には、コンクリート以外にも様々な方法があり、それぞれに一長一短があります。
ここでは、代表的な雑草対策とコンクリートを、費用・耐久性・メンテナンス性といったプロの視点で徹底的に比較し、あなたが後悔しないための最終的な判断材料をご提供します。
コンクリートVS防草シート+砂利敷き

費用を抑えたいと考えたとき、まず候補に挙がるのがこの「防草シート+砂利敷き」ですよね。初期費用だけで見れば、コンクリートに比べて圧倒的に安価なのが最大のメリットです。
DIYで挑戦される方も多いですね。しかし、ここで考えていただきたいのが、10年後のお庭の姿です。
防草シートの耐用年数(単体の曝露施工の場合)は、製品にもよりますが一般的に5年~10年。やがて劣化して破れた箇所から、しつこい雑草が突き抜けてきます。
そして何より、私がお客様からよくご相談いただくのが「落ち葉掃除が絶望的に大変」だという点。砂利の上に積もった落ち葉は、ホウキでは掃けず、ブロワーを使えば砂利ごと飛んでいってしまう。結局、手で拾うしかなく、コンクリートの掃除の手軽さとは比べ物になりません。
初期費用は安いですが、長期的なメンテナンスの手間と再施工のコストまで含めると、一概に「安い」とは言えないのが実情です。

コンクリートVS固まる土(防草土)

「コンクリートの無機質な感じは嫌だけど、砂利の手間も…」そんな方に人気なのが、土のような自然な風合いが魅力の「固まる土」です。
水をかけるとカチカチに固まる土で、DIYで施工できる手軽さもあってホームセンターなどでもよく見かけますね。
人が歩く程度の玄関アプローチや、お庭の小道など、景観を重視しつつ、あまり負荷のかからない場所には適しています。しかし、その強度はコンクリートには遠く及びません。
車の乗り入れはもちろん不可能ですし、人が頻繁に歩く場所では、表面が削れて徐々に薄くなっていきます。また、水はけが悪い場所では、コケが生えたり、冬場の凍結でひび割れが起きやすいという弱点も。
「簡易的な舗装」と捉え、コンクリートと同じような永続的な強度を期待しないことが、上手に付き合うポイントです。
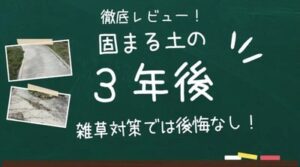
コンクリートVS人工芝

「雑草の手間は無くしたいけど、お庭の緑は失いたくない!」そんなご要望に完璧に応えてくれるのが「人工芝」です。
最近の人工芝は非常にリアルで、一年中青々とした美しい景観を保つことができます。お子様やペットが走り回っても安全で、クッション性があるのも魅力ですね。
ただし、高品質な人工芝とその下地工事の費用は、実は土間コンクリートと同等か、それ以上になることも少なくありません。
美しい状態を保つには、芝目を立たせるためのブラッシングや、ゴミの掃除といった定期的なメンテナンスも必要です。そして何より、夏場は直射日光で表面が高温になりやすいというデメリットも。
用途が大きく異なり、「緑の景観」を最優先するなら人工芝、「硬く、多目的なスペース」を求めるならコンクリート、という風に、お庭で何をしたいかによって選ぶべきものが変わってきます。

コンクリートVSモルタル仕上げ

DIYをされる方から時々「コンクリートとモルタル、何が違うの?」とご質問をいただきます。これは非常に重要なポイントです。
簡単に言うと、「砂利(砕石)」が入っているのがコンクリート、入っていないのがモルタルです。この砂利(砕石)こそが、強度を出すための骨材の役割を果たしています。
モルタルは、主にレンガの目地を埋めたり、ブロック塀の表面を薄く塗ったりする「仕上げ材」や「接着剤」として使われるもので、構造的な強度はありません。
そのため、駐車場やお庭の地面のように、人が歩いたり車が乗ったりする場所の舗装にモルタルを使うのは、基本的にやめた方がいいでしょう。必ずひび割れや破損に繋がります。用途が全く違うということを、しっかりと覚えておいていただければと思います。
さて、様々な比較をしてきましたが、それでもまだ細かい疑問は残りますよね。次の章では、お客様からよくいただく質問にお答えするQ&Aコーナーです。
⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません
ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。
間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。
そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。
奈良県限定!
雑草対策コンクリートに関するQ&A
ここまでコンクリートに関する様々な情報をお伝えしてきましたが、いざご自身の庭に置き換えて考えると、まだ個別の疑問や不安が残っているかもしれませんね。
この章では、私がお客様との打ち合わせの場で、本当によくいただくご質問をいくつかピックアップし、プロの視点から正直にお答えしていきます。皆さんが抱える最後の「?」を、ここでスッキリ解消していきましょう。
コンクリートで雑草対策をするのにいくらかかりますか?
これは、やはり一番多いご質問ですね。記事の前半でも詳しく解説しましたが、我々のようなプロが施工する場合、1平方メートルあたり10,000円~15,000円というのが一つの目安になります。この金額には、地面を掘って固める下地作りから、強度を保つためのワイヤーメッシュ、そして表面を美しく仕上げる左官作業まで、必要な工程がすべて含まれています。
もちろん、敷地の条件によって価格は変動します。より詳しい面積別のシミュレーションや、費用を賢く抑えるコツについては、「【費用を徹底比較】庭のコンクリート料金相場と安く抑えるコツ」の章で詳しく解説していますので、ぜひそちらをもう一度ご覧になってみてください。
コンクリートの隙間から雑草が生えてくることはある?
「コンクリートにすれば、もう雑草は一本も生えてこないんですよね?」と期待されるのですが、これについては「はい、残念ながら可能性はゼロではありません」と正直にお答えしています。理由は、経年で生じた細かなひび割れ(クラック)に土が溜まり、そこに種子が根付くケース。そして、伸縮性により壁や建物の基礎との間に数ミリの隙間ができてしまい、そこから雑草がが生えてくることがあります。
雑草対策にコンクリートの厚みはどのくらい必要ですか?
これは非常に重要なポイントで、コンクリートの寿命を左右すると言っても過言ではありません。我々プロの世界では、厚さ10cmというのが絶対的な基準になります。特に、駐車場のように車の重量がかかる場所であれば、この10cmの厚さに加え、強度を補強するためのワイヤーメッシュ(鉄筋)を入れることが必須です。
人が歩くだけの通路などであれば7~8cmでも問題ない場合もありますが、長期的な耐久性を考えると、やはり10cmを確保しておくのが最も安心です
土間コンクリートを敷いたら固定資産税はかかりますか
これも時々ご心配される方がいらっしゃいますが、ご安心ください。一般的なご家庭のお庭や駐車場に、雑草対策として土間コンクリートを敷設しただけで、原則として固定資産税の課税対象とはなりません。固定資産税がかかるのは、基本的に屋根と壁のある「家屋」や、事業用の「構築物」です。
外構や 庭をコンクリートにすることによるデメリットは?
この記事でも詳しく解説してきましたが、最後におさらいとして重要なデメリットを3つ挙げておきますね。まず一つ目は、「夏の強烈な照り返しと蓄熱」です。表面が高温になり、小さなお子様やペットには注意が必要です。
二つ目は、「土壌環境の不可逆性」。一度施工すると、その場所を家庭菜園などの土の状態に戻すことは極めて困難になります。そして三つ目が、「地下配管トラブル時のリスク」です。万が一、地面の下の水道管などが破損した場合、修繕のためにコンクリートを破壊する必要があり、高額な追加工事費が発生する可能性があります。これらの点を許容できるかが、最終的な判断の分かれ目になります。
さて、全ての疑問は解消されたでしょうか。最後の章では、ここまでの内容を踏まえ、あなたが後悔しないための最終チェックリストをご用意しました。
まとめ
庭の雑草対策としてコンクリートは、毎年の面倒な草むしりから解放され、時間と心のゆとりを生み出す強力な解決策です。
その効果は絶大ですが、夏の照り返しや、一度施工すると家庭菜園などができなくなる「不可逆性」、そして万が一の「地下配管トラブル」といった、事前に知っておくべきデメリットも存在します。
大切なのは費用だけでなく、こうしたメリット・デメリットの両方を天秤にかけ、10年、20年先のご自身の暮らしにとって本当にプラスになるかを見極めること。
この記事が、あなたの後悔しないお庭づくりの一助となれば幸いです。最終的な判断に迷われた際は、ぜひ一度、私たちのような専門家にご相談くださいね。